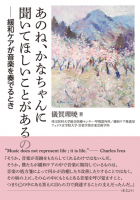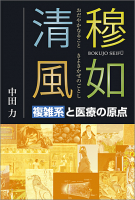お知らせ
寝たきり患者は急性期病院でつくられる[炉辺閑話]
2018年度の医療費は、対前年比3400億円増の42兆6000億円です。2018年には50兆円を超えると予想されていた2012年の予想とはずいぶん違った方向に進んでいます。政府は、医療や介護を利用する国民がどんどん増えるのを何とか抑制しようとしています。どうやらその効果が出ているようです。
世の中が大きく変わってきました。私は今後、総医療費は、超高齢化にもかかわらず、そんなに増えないと思っています。

厚生労働省の介護保険部会等において、将来の介護費用や介護職員の不足について喧々諤々の議論が交わされています。しかも、それは要介護者が一方的に増加するという固定概念のもとに話が進められているのです。
しかし、高齢者が要介護状態となる前には必ず医療が必要な状態となる時期があるのです。つまり、日本の医療提供体制に問題があるのではないでしょうか。
急性期病院の入院患者に占める高齢者の割合が30年前の倍の約75%となっています。しかし、病棟の看護職員の数は2006年の7対1看護配置が始まったときと変わっていません。介護ケアの必要な高齢者が倍増しているのに、介護職員は配置されていません。
だから急性期病院の現場では、行動が不安定な高齢者のために膀胱留置バルーンカテーテルを留置し、認知症状を呈する患者には身体拘束をするなどして、高齢者は身体の自由を奪われ、1カ月後には完全な寝たきり状態となってしまっているのです。急性期治療後を受け持つ慢性期病院でも、そのような状態できた患者はそのままにしている病院も多いのです。しかし、良心的な慢性期病院では、転院後直ちにバルーンを抜去し、身体拘束はしません。しかしながら、既に急性期病院で長期間つらい目に遭っていた患者さんの目はうつろ。それでもリハビリテーションをして、何とか元の日常生活に戻そうと努力している病院には本当に頭が下がります。
急性期病院でこれらの行為を限りなく減らすことができれば、要介護高齢者は劇的に減るでしょう。そうすれば、医療費や介護費も減らすことができるでしょう。介護保険関係者は、寝たきりをつくっている急性期病院の現場に意見を言うべきです。