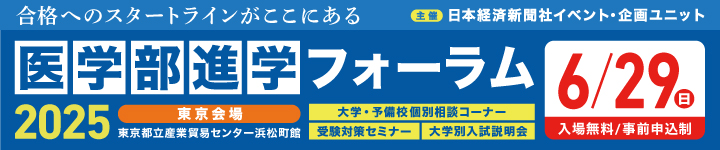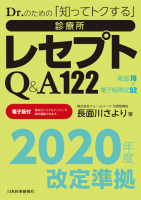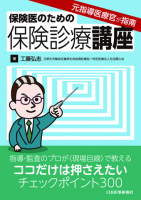お知らせ
■NEWS 「小児かかりつけ診療料」の算定促進が次期改定の課題に―中医協
中央社会保険医療協議会は8月2日、次期診療報酬改定に向けて小児医療と周産期医療について議論した。小児医療では、前回改定で時間外対応の基準を緩和した算定区分を新設したにもかかわらず、「小児かかりつけ診療料」の算定が依然として低調であることが明らかになった。
「小児かかりつけ診療料」は、小児科を標榜する医療機関のかかりつけ医機能の評価で、自院を4回以上受診した未就学児を対象に算定。施設基準では、保護者からの診療時間外の問い合わせなどに対応できるよう、「時間外対応加算」の届出などを求めている。

2022年度の前回改定以前の施設基準では、「時間外対応加算1、2」のいずれかの届出が必須とされていたが、この規定が「小児かかりつけ診療料」の算定が伸びない原因にもなっていた。このため22年度改定では、この部分の基準を緩めた「小児かかりつけ診療料2」を新設。他の医療機関との連携で時間外対応を行っている「時間外対応加算3」の届出や、在宅当番医制等への参加でも算定が可能になった。
■「小児かかりつけ診療料」の算定は6歳未満の「初・再診料」等の1割程度
その結果、「小児かかりつけ診療料」の算定回数と届出医療機関数は21年から22年にかけて増加したが、6歳未満の小児における「初・再診料」等(「外来診療料」含む)の算定回数に比べると、10%程度と低い水準にとどまっている。
診療側の長島公之委員(日本医師会常任理事)は、「小児かかりつけ診療料2」を新設した経緯を、24時間の診療は必要ないが、助言や医療機関の紹介はしてほしいという患者の要望に応えたものだと振り返り、「地域で様々な役割を果たしている医療機関を評価するという視点は次回改定でも重要だ」と述べた。
これに対して支払側の松本真人委員(健康保険組合連合会理事)は、「24時間対応は、かかりつけ医機能の極めて重要な要素であり、これ以上の要件緩和は厳しい」と牽制。「時間外対応加算3」とともに施設基準に定められている、在宅当番医制への参加促進などを通じて算定医療機関の拡大を図っていくべきだと主張した。
一方、周産期医療では、総合周産期母子医療センター等の基幹病院を中心に医療機関・機能の集約化を進めていくことが医療計画上の課題となっており、こうした体制整備を支える診療報酬のあり方や、ハイリスク妊産婦への対応などが論点として提示された。