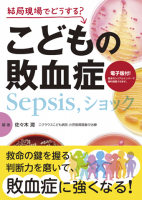お知らせ
【識者の眼】「子どもの溺水を防ぐには」坂本昌彦
今年の夏も子どもの溺水事故が相次ぎました。相次ぐ事故のニュースに胸が苦しくなる思いです。
どうしてこんなに多いのかと思われる方もいらっしゃるかもしれません。人口動態統計によると2021年は14歳以下の小児が47名溺水で亡くなっています。しかし35年前の1986年の溺水による小児の死亡数は年間665名ですので、人数としては大きく減っています。減った原因としては少子化や用水路の減少といった社会的な要因に加え、遊泳区域の管理体制の強化、監視体制の整備なども挙げられると思います。この5年ほどは年間50人前後と横ばいなので、それをいかにゼロに近づけられるかが今の課題です。
子どもの溺水は4歳以下の乳幼児と18歳をピークとする中高生に多いことがわかっています。死亡したり神経学的後遺症を残したりするリスクが高いのは、水没時間が6分を超える場合、蘇生時間が長期にわたる場合、居合わせた人による心肺蘇生がなされていない場合、とされます。悲しい事故を防ぐ対策として、米国小児科学会が19年に出した声明からポイントを抜粋してご紹介します。
まずは子どもだけで自然水域に近づかせないことです。ただし、子どもだけで事故が起きているのは全体の3割で、7割近くは大人と一緒の時に事故が起きています。大人と一緒だから大丈夫とは言えない点に注意が必要です。
次にライフジャケット着用です。最近メディアで「浮いて待て」が対策として有効というニュースも目にしますが、静水域はともかく、激しく不規則な流れの川ではうまく浮かばずパニックになり溺れます。それだけでは有効な予防策にはなりません。一方ライフジャケット着用は有効性が証明され、米国小児科学会でも特にその有用性が強調されています。乗車時のシートベルトと同じように、自然水域では習慣にすべきです。ちなみにライフジャケットは正しいサイズと装着方法が重要である点も強調したい点です。
そして監視体制です。複数の大人がいても、誰かが見ていると思って誰も見ていないことがあるので、時間帯で責任を持つ監視役を必ず決めることが重要です。なお、ライフガードや監視員がいるから大丈夫とはいえません。米国のプールの水難事故の1/3以上が監視員のいるプールで起きています。背景に監視員の長時間労働などによる監視の質の低下も指摘されており、監視の有無だけでなく質の議論も重要です。
また水の安全に関する知識を身につけることです。自然水域には危険な流れの起きやすい場所があります。さらに、溺水者発見時の対応を誤ると、救助に赴いた人が二次災害で亡くなることもあります(約15%で発生するとされています)。やみくもに飛び込まず、安全な救助方法を知ることが大切です。これらの情報をあらかじめ知っておくことは水難事故の予防につながります。河川財団の「水辺の安全ハンドブック」がよくまとまっていてわかりやすいです。
最後に心肺蘇生です。溺水後の生存率や神経学的予後改善の上でもっとも有効とされており、これを機に、あらためて心肺蘇生法の啓発を進めるきっかけになればと思います。
坂本昌彦(佐久総合病院・佐久医療センター小児科医長)[米国小児科学会声明][心肺蘇生法]