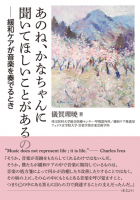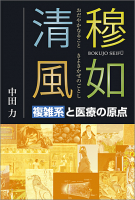お知らせ
小児のシェーグレン症候群(伊藤保彦)[プラタナス]
私は1988年から3年間、自己抗体の研究のために留学し、特に抗Ro抗体の研究に力を注いで帰国した。ところが、当時の小児科は「そもそも小児の膠原病患者は非常に稀だし、ましてシェーグレン症候群の自己抗体など、まったく役に立たない研究をしてきたものだ」という冷めた雰囲気だった。私自身もそんな感覚があったのは事実で、それでも研究に没頭した3年間は無駄にはなるまいと自分に言い聞かせていた。
尋常ならざる高γ-グロブリン血症をみて、研究中に読んだ論文に「抗Ro抗体陽性患者は顕著な高γ-グロブリン血症を呈しやすく、時に全IgGの90%以上を抗Ro抗体が占める」と書いてあったのを思い出した。さっそく、追加の検査を提出したところ、抗核抗体2560倍(Speckled)、抗Ro抗体149.3U/mL、抗La抗体192.5U/mLという結果が返ってきた。この患者の紫斑は高γ-グロブリン血症によるものだったのだ。5歳の小児にもシェーグレン症候群が発症するという事実を目の当たりにして、私は小児膠原病の専門家をめざそうと決意したのだった。

その後、日常診療でしばしば経験する慢性的に不定愁訴を訴える子どもたちに抗核抗体陽性者が多いこと、その10%前後は抗Ro抗体陽性であることを見出した。それらの患者は乾燥症状もなく、シェーグレン症候群の診断基準は満たしていない。しかし、長年経過を観察すると、しだいに診断基準を満たすものが現れてきた。成人期に発症すると考えられていたシェーグレン症候群だが、既に小児期から抗Ro抗体が出現しており、乾燥症状は外分泌腺の破壊が進んでから現れる末期症状なのだ。今回提示した症例は、たまたま紫斑という形で小児期に発症したが、多くのシェーグレン症候群患者は小児期にその萌芽があり、我々小児科医が見過ごしているということを強調しておきたい。