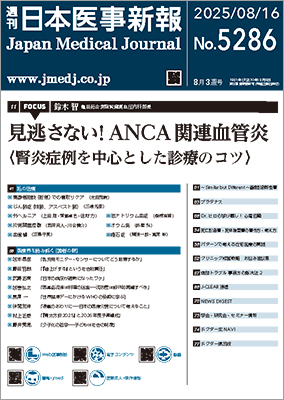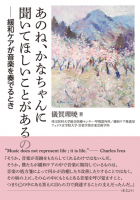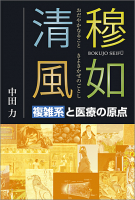お知らせ
卵円孔の開存[先生、ご存知ですか(75)]
脳梗塞の原因
脳梗塞の原因として、アテローム血栓性脳梗塞、ラクナ梗塞、心原性脳塞栓症が知られています。しかし、脳梗塞にはこれ以外の原因によるもの、あるいは原因不明なものもあります。これに含まれるものとして、卵円孔開存による脳梗塞があります。
下肢などの深部静脈に血栓があると、血流に乗って右心房に血栓が流入します。その血栓が開存している卵円孔を通って左心系に移動し、その結果生じる脳梗塞を奇異性脳塞栓と呼びます。

海外の研究によると、卵円孔が開存している成人では、周術期に脳梗塞を発症するリスクが高く、オッズ比は2.66でした。そして、1000例当たりの脳梗塞推定発症率は卵円孔開存群で5.9例、非開存群で2.2例でした。
卵円孔が開存すること
卵円孔は、出生後に肺血流増加に伴って左心房圧が上昇し、一次中隔と二次中隔の弁構造が圧によって押しつけられて、出生早期に物理的に閉鎖します。そして、その後に結合組織が増殖して弁構造が固定化され器質化することにより、生後2~3カ月頃に閉鎖が完成します。
右心房と左心房の間に卵円窩という部分があり、これが閉鎖した卵円孔に相当します。よく観察すると、閉鎖しているようにみえても、重なった2枚の膜(一次中隔と二次中隔)に開存部分があることや、トンネル構造がみられることがあり、これが卵円孔の開存と言われています。開存部分の大きさを計測した報告では、直径が3.5~6.3mmとのことです。
どのくらいの頻度か
卵円孔開存の頻度の測定については、心エコーやカテーテル検査など、生体を対象にした検査に基づく方法と、剖検例に基づく方法があります。もちろん、剖検例は直接観察によりますので、正確です。
海外では古くから剖検例に基づく報告がありますが、5歳以下では開存率が50%、成人では20~25%とのことです。剖検例でも、病理解剖ではもともと何らかの疾患を有する人を対象にしていますから、健常成人の頻度とは言えません。また、上記のように小さい孔やトンネルですので、細かく観察しなければわかりません。
そこで、筆者らは突然死や外傷例に基づく法医剖検例を対象に、卵円孔の開存頻度を調査しました。すると、20歳以上の成人男性では、年齢群ごとに調べても開存率が9.1~17.6%、成人女性では5.6~20%でした。かつて国内で行われた、約100例の病理解剖例をもとにした卵円孔の開存頻度の調査によると、60~79歳における開存率が13.8%とのことで、筆者らのデータと同様です。これらの頻度は、海外で報告されてきた値より低いのが特徴です。
なお、筆者らは卵円窩の面積を計測しましたが、心臓重量に依存することもわかりました。すなわち、心臓重量当たりの大きさは、ほぼ一定でした。
日本人を対象とした調査の重要性
卵円孔の閉鎖については発生学的機序が関与していますが、人種差があると考えられます。医学における様々な分野では、外国人を対象とした頻度が報告されていても、日本人での報告がないものもあります。やはり、日本人を対象とした調査の重要性を再認識しました。