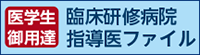お知らせ
【識者の眼】「生活習慣病管理料とICT」土屋淳郎
今回の診療報酬改定で高血圧・糖尿病・脂質異常症が特定疾患療養管理料から除外されたのは、これら疾患の重症化の先にある種々の疾患を予防するために疾病管理を徹底し、さらには患者の意識も高めていくことが主目的だと認識はしているものの、何もしなければ減算されるのでなんとかしなくてはならない、むしろ余計なことをやらされているのかも? というネガティブな心理状態に陥りそうになる。
そんな自身を鼓舞するためにも、これらの対応がかかりつけ医のDXにポジティブに働くと前向きに考えいろいろと調べてみると、生活習慣病管理料の算定に関わるICTシステムはいくつもある。主な機能としては、療養計画書の作成を支援するもの、患者個別の指導内容を支援するもの、算定状況などの管理を支援するもの、患者の行動記録などと連携し行動変容を支援するものなどがあり、これらの機能を組み合わせているシステムが多い印象だ。

筆者の診療所では、既に利用している検査情報管理+医療文書作成支援システムと、Web問診システムと患者管理システムを複合したシステムをバージョンアップして利用し、高血圧に関しては高血圧症治療補助プログラムを利用して患者の行動記録と連携するような運用にしていく方針を考えている。余談ではあるが、多機能型電子カルテは使い勝手の悪い機能も多いので、シンプルな機能の電子カルテと、必要な追加機能に特化したシステムを連携する仕組みになればよいと考えているため、自院では様々なシステムを利用しているのだが、システム連携には何かと手間のかかる状況もあるのが実情だ。
さて、今回の生活習慣病管理料の算定に関わるICTシステムについては、これらを利用しても診療所の収益が大幅に増加することはないので、企業も費用をそれほど高額には設定していない印象を持っている。もちろん診療所としては手間が減る、管理が楽になる、指導内容などの情報が手に入れやすくなるといったメリットを感じ、患者さんにとっても病状や予後がよくなるという効果が得られるのであればそれに見合ったコストを支払うことは悪くない。とはいえ、疾病管理の徹底による重症化予防の受益者は保険者と患者であり、投資者は医療機関であるという構図はいつもと変わりはないし、診療報酬に振り回されて現状維持もままならない状況を目の当たりにすると、今後の医療保険制度への不安が大きくなり、またネガティブな心理状態に陥りそうである。
土屋淳郎(医療法人社団創成会土屋医院院長、全国医療介護連携ネットワーク研究会会長)[診療報酬改定][医療保険の将来]