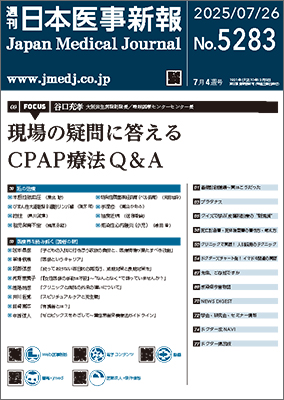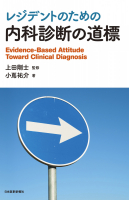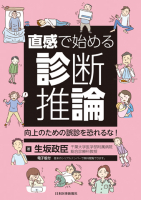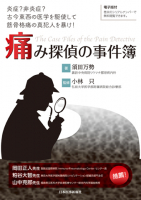お知らせ
【識者の眼】「アジア太平洋地域の家庭医推進に向けて②」草場鉄周
前回(No.5225)の予告通り、6月7〜9日に浜松で開催された第15回日本プライマリ・ケア連合学会学術大会における「アジア太平洋地域の家庭医療推進に向けて」シンポジウムの模様をお届けする。
シンポジウムに先立ち、世界家庭医療機構(WONCA)の前会長のAnna Stavdal(ノルウェー)が「Continuity of care in times of continuous change」と題した基調講演を行い、常に変化する世界で医療の断片化、商業化、医療サービス提供のデジタル化が進む中、プライマリ・ケアの基盤となる継続的なケアが危機的な状況にあること、そして、我々家庭医はその変化を拒むのではなく、むしろ医療提供のあり方を次のステップに昇華させることの重要性を提起した。

続くシンポジウムでは、WONCA アジア太平洋地域(APR)会長のBrian Chang(台湾)がWONCA APRの概要とミッションを紹介した。WONCA APR総務担当理事のAileen Riel-Espina(フィリピン)はWONCA APRの50年の歴史を丁寧にひもとき、この地域がWONCAの中核として世界に貢献してきた業績を紹介した。WONCA APR財務担当理事の筆者は、開催国の立場から日本のプライマリ・ケアの国際活動の歴史を紹介し、その活動の中核にはWONCAとの関係が常に位置づけられ、ようやくここ10年ほどで日本からアジアや世界に発信する準備が整ってきたことをアピールした。
日本から発信する3つの軸として、①超高齢化社会におけるプライマリ・ケアの役割、②臓器別専門医からプライマリ・ケアに転じた医師への生涯教育、③アジア太平洋地域の研究ネットワーク─を提唱した。特に①については、アジア太平洋地域のみならず、世界全体でも日本は超高齢化のトップランナーであり、それに伴う様々な社会課題が既に表出されつつあることから、プライマリ・ケアもその解決の一端を担う必要があることは言うまでもない。医療制度や文化の相違はあるが、地球の気候変動問題と同じく、高齢化はグローバルな課題としてとらえる必要があり、日本はその経験と対応について世界に伝える義務を持つと言ってよいだろう。
今回の基調講演とシンポジウムをきっかけに、日本のプライマリ・ケアも世界から学び世界に貢献する姿勢をさらに進めていき、次世代につないでいきたいと切に思う。
草場鉄周(日本プライマリ・ケア連合学会理事長、医療法人北海道家庭医療学センター理事長)[総合診療/家庭医療]