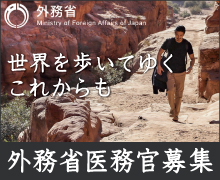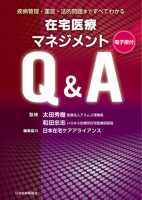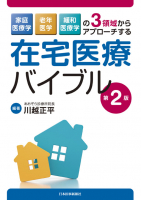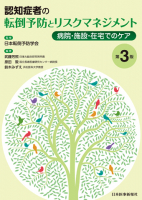お知らせ
連携における役割と課題(歯科医・歯科衛生士)[私の治療]
「肺炎は老人の友」とも言われており,在宅患者の多くを占める高齢者は,誤嚥性肺炎のリスクが高い。1999年にLancetに発表された米山らの論文1)より,歯科医療従事者が専門的口腔ケアを行うことで,誤嚥性肺炎を防げることが明らかとなった。そのためわが国では歯科が在宅医療に積極的に関わるという,世界的にみても先進的な取り組みが行われている。近年はさらにそれを推し進め,歯科が摂食嚥下機能の向上や栄養ケアにも関わることで,在宅療養高齢者のQOL向上に寄与する取り組みが広まってきており,2024年度診療報酬・介護報酬改定(以下,2024年度改定)においても評価されている。しかし,歯科との連携の取り組みの実施状況については,地域差がかなり大きいのが実情である。
▶在宅医療において歯科と連携すべき項目
【誤嚥性肺炎の予防】
誤嚥性肺炎の予防には,①誤嚥量を減らす,②誤嚥してしまった唾液中の細菌数を減らす,③誤嚥しても肺炎につながらない体力をつける,が重要となる。中でも歯科は,②の細菌数の減少を,口腔衛生管理(いわゆる専門的口腔ケア)で担当する。2024年度改定より,在宅療養者に対して,口腔内細菌カウンターを使用して口腔衛生状態を定量的に評価し,継続的に管理を行うことが認められるようになった。
【感染・疼痛管理】
口腔内は,う蝕や歯周病といった慢性感染症が歯や骨といった硬組織に長期にわたって存在するという特殊な環境である。特に歯周炎や根尖病巣の細菌が,血行性に体内に移行してしまう病巣感染は,感染性心内膜炎などの原因としてよく知られている。また細菌を原因とする口腔内の慢性炎症は,咀嚼時の痛みの原因でもあり,処置として抜歯を選択せざるをえないケースも多く存在する。

残り1,484文字あります
会員登録頂くことで利用範囲が広がります。 » 会員登録する