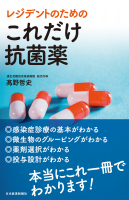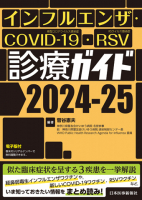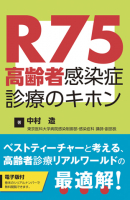お知らせ
日本紅斑熱[私の治療]

日本紅斑熱は1984年に初めて報告され,1999年に感染症法の4類に分類されたリケッチア感染症で,マダニに咬まれることで発症する。関東以西の温暖な地域で多いとされてきたが,届出地域は拡大している。βラクタム系抗菌薬が無効であり,また重症化することもある疾患であることから,病歴聴取と身体所見から鑑別疾患を挙げ,疑われた際には早急に治療を行うべき疾患である。
▶診断のポイント
発熱,倦怠感,頭痛など非特異的な症状で発症する。これらの症状と,14日以内の山歩きや庭作業歴など自然との接触歴の聴取,マダニによる刺し口やマダニ虫体の付着の全身検索(特に腋窩や膝窩,陰部や腕時計の下の皮膚などを確認する。マダニ咬傷は痛みがないため,気づかれにくいことから視診は特に重要),潰瘍もしくは痂皮を伴う紅斑の確認が診断に有用である。確定診断は痂皮・血液のPCR検査や,急性期と回復期のペア血清による抗体価上昇の確認である(いずれの検査も地域の保健所や衛生研究所に相談し,確定診断を得たら直ちに発生届を提出する)。

マダニが媒介する疾患はほかにツツガムシ病や重症熱性血小板減少症候群(SFTS)がある。ツツガムシ病と比べて,日本紅斑熱は春~夏に多く(ツツガムシ病は秋以降に多い),手掌・足底の皮疹が優位で,低ナトリウム血症や臓器障害がみられ,治療後の解熱までの期間が長いなどの特徴が報告されている1)。また,SFTSと比べて,日本紅斑熱は皮疹がみられるが意識障害を伴わないことや,白血球数が4000/μL以上であることが特徴として報告されている2)ので参考にされたい。
▶私の治療方針・処方の組み立て方
重症化することもあり,病歴や身体所見から日本紅斑熱を疑ったら,検査を依頼しつつ,早急に治療を開始する。
病原体である日本紅斑熱リケッチア(Rickettsia japonica)は,結核菌,Legionella属,Chlamydia pneumoniaeなどと同様の細胞内寄生菌である。そのため,細胞壁合成阻害薬であるβラクタム系抗菌薬(ペニシリン系,セフェム系,カルバペネム系など)は無効である。蛋白質合成阻害薬であるテトラサイクリン系(ドキシサイクリン,ミノサイクリン等)が第一選択薬となる。テトラサイクリン系抗菌薬の生体利用率は高く,内服でも90%程度とされている。
重症の日本紅斑熱症例に対するテトラサイクリン系抗菌薬とフルオロキノロン系抗菌薬の併用療法はこれまで賛否両論あり,十分なエビデンスに乏しい状況が続いている。近年,1060例の日本紅斑熱症例を対象に,テトラサイクリン系抗菌薬単剤と,テトラサイクリン系抗菌薬・フルオロキノロン系抗菌薬併用群を後方視的に比較した研究が発表された3)。その結果は,両群で院内死亡率,集中治療率,総入院費用,入院期間のいずれも有意差が示されなかった。フルオロキノロン系抗菌薬併用に伴う有害事象(腎障害,消化管症状等)を考慮し,本稿ではテトラサイクリン系抗菌薬単剤での加療を提案する。

残り957文字あります
会員登録頂くことで利用範囲が広がります。 » 会員登録する