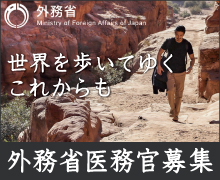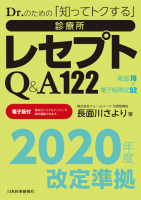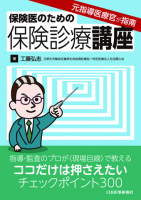お知らせ
■NEWS 「一般名処方加算」の引上げで一般名処方が増加―24年度改定検証調査
4月9日に公表された2024年度診療報酬改定の検証調査の結果によると、「一般名処方加算」の引上げで診療所の一般名処方の件数は改定前よりも増加したことが分かった。一方、後発医薬品の供給体制に関しては、1年前よりも悪化したとの回答が診療所の約5割、病院の約6割を占めた。
24年度改定では後発医薬品の使用促進策の一環として、「処方箋料」における「一般名処方加算」「外来後発医薬品使用体制加算」などの評価引上げ、長期収載品の使用の選定療養化などを実施。特別調査では、診療所、病院、医師、患者などを対象に、一般名処方の実施や後発医薬品の使用、患者の後発医薬品に対する意識への影響を検証した。

診療所調査で一般名処方の実績ありと回答した施設に1年前と比較した「一般名処方加算」の算定回数を聞いたところ、43.8%が「増えた」と回答。理由として最も多いのは「一般名処方加算の点数が引き上げられたから」(34.2%)、次いで「先発医薬品を希望する患者が減ったから」(26.5%)、「一般名処方に対応できる院内体制が整備されたから」(25.6%)など。これに対し一般名処方の件数が「変わらない」、「減った」と答えた施設の理由は、「後発医薬品の安定供給への不安があるから」(27.9%)が最も多かった。
■後発品供給体制、過半数の医療機関が1年前よりも悪化
後発医薬品の供給体制が1年前と比べて「悪化した」と回答した診療所は53.4%、病院は63.3%と「改善した」(診療所5.0%、病院0.9%)を大きく上回った。後発医薬品の処方割合については「変化はほとんどなかった」(診療所35.1%、病院49.3%)が診療所、病院とも最多となった。後発医薬品の使用促進に必要な対応では、診療所の65.8%、病院の90.8%が「後発医薬品に関する安定供給体制の確保」を挙げた。
患者調査の結果をみると、長期収載品の使用の選定療養化を「知っていた」割合は、郵送調査67.9%、インターネット調査31.9%。後発医薬品の使用に関する考え方は、郵送調査では「後発医薬品や先発医薬品にこだわらない」(41.6%)、ネット調査では「できれば後発医薬品を使いたい」(42.4%)がそれぞれ最も多かった。バイオ後続品の認知度は極めて低く、「知っている」と答えたのは郵送調査18.9%、ネット調査8.9%にとどまった。