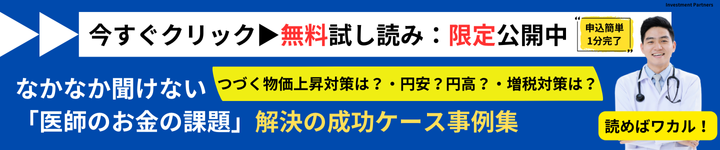お知らせ
精神医学的漱石論(2)─作家・評論家による病跡学 [エッセイ]
ドナルド・キーンの『日本文学史』
1984(昭和59)年に発表されたドナルド・キーンの『日本文学史 近代・現代篇二』(徳岡孝夫訳、中央公論社刊)では、漱石の精神病理的な部分への言及がなされているが、キーンが語る病跡学的な見解にはいくつかの不可解な点がある。
第一は、キーンが1896(明治29)~1900(33)年の熊本における漱石の新婚生活に触れた部分で、「家庭生活は最初からうまくいかなかった」として、鏡子夫人が「繰り返し強度の神経衰弱に陥る夫を狂人かと思い疑った」と述べていることである。キーンは、明治29年の結婚当初から漱石には病的な症状があって、鏡子夫人もそれを認識していたとしているわけであるが、これは、1929(昭和4)年に発表された鏡子夫人の『漱石の思ひ出』(岩波書店刊)の中の「洋行を転機として、私ども一家の上に暗い影がさすようになってまいりました」という記述と、矛盾する。鏡子夫人は、漱石の精神状態が不安定になったのはあくまでも明治33年に洋行してからのことであり、それに先立つ熊本時代の漱石は安定していた、と語っているのである。
したがって、キーンが、英国留学中の漱石の精神状態について、「ロンドン生活の孤独と憂鬱は、すでに妻の鏡子が発見し恐れていた漱石の不安定な精神状態を悪化させる原因になった」としているのも不正確な記述で、留学以前に鏡子夫人が漱石の不安定な精神状態を発見し恐れていたわけではないのである。
第二は、1903(明治36)年に帰国してからの漱石の精神状態について、1904(明治37)年前半までは、「ロンドン時代に彼を苦しめた偏執病も再び頭をもたげ、他人に追跡、監視されていると思い込み、探偵(刑事)に対して病的なまでの猜疑心を抱くようになった」と述べる一方で、1905(明治38)年に『吾輩は猫である』を執筆するようになってからは、「折から鬱病のはげしい発作に襲われていた」と述べていることである。すなわち、キーンは、明治36、7年頃の漱石は偏執病だったが、明治38、9年頃は鬱病だったとしているわけで、それではいつ偏執病が鬱病になったのか、それぞれの具体的な症状は何か、などについての説明がなされていないため、明治30年代後半の漱石には相矛盾する診断名が並立する形になっている。
第三は、漱石が1907(明治40)年に東大を辞して、朝日新聞社に入社した事情である。キーンは、漱石が朝日新聞紙上に発表した『入社の辞』(『漱石全集第21巻』、岩波書店刊)の内容を要約する形で「大学との契約も一区切りがつき、かつまた創作に没頭すべき時に来ていることなどの理由をあげて、自己の転職を説明している」と紹介している。しかし、実は『入社の辞』の中で漱石は、「大学で講義をするときは、いつでも犬が吠えて不愉快であった。余の講義のまずかったのも半分はこの犬のためである」、「余が閲覧室へ這入ると隣室にいる館員が、無暗に大きな声で話をする、笑う、ふざける」などと、被害妄想めいたことを語っているのである。
したがって、漱石が東大を辞めたことの背景には、東大に対する被害妄想という病的な要素も考慮する必要があるのだが、キーンの紹介では、当時の価値観からすれば非常識とも思える漱石の転身の背後にある病的な要素を見逃した形になっている。
残り1,235文字あります
会員登録頂くことで利用範囲が広がります。 » 会員登録する