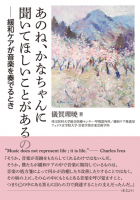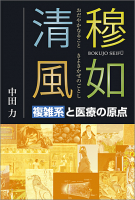お知らせ
子どもの自殺が減らない[先生、ご存知ですか(76)]
滋賀県の子どもの死因別分類では自殺が2位に
滋賀県では18歳未満の子どもの死亡例を収集し、死因や死亡に至った経緯を詳細に分析しています(child death review)。そして、防ぎうる死亡を減らす取り組みや、死が避けられない子どもが最期まで質の高い生活を送れるような対策を検討しています。
2023年における滋賀県の子どもの死因として最も多かったのは病死で、69%を占めました。それに続くのが自殺で、14%でした。これは、交通事故の7%や溺水の5%といった不慮の事故を上回りました。滋賀県では、子どもの死因別分類で自殺が2位になるのは初めてのことです。全国をみても、2023年における小中高生の自殺者は507人と、2022年に続いて500人を超えている状態です。このように子どもの自殺者が多いことは大きな社会問題です。

コロナ禍での自殺増加
わが国では2009年に3万2845人であった自殺者が2019年まで減少し続けていました。しかし、コロナ禍の2020年に再度自殺者が増加し2万1081人となりました。人流や対人接触が減ることで経済的な打撃を受けた業種が多く、その結果、アルバイトなどの若者の失業、家庭にとどまることが多くなったことによる家庭内不和などが原因となりました。
自殺の背景には、精神障害が関与していることはよく知られています。ある研究によると、救命救急センターに搬送された重傷自殺者の23%がうつ病などの気分障害、19%が適応障害であったそうです。特にコロナ禍では、子どものメンタルヘルスにも影響が生じました。コロナ禍前には、小学4年生から中学1年生までのうつ病の有病率は1.5%であったそうですが、コロナ禍の2021年12月には、小学5, 6年生の9~13%、中学生の13~22%に中等度以上のうつ症状がみられたそうです。コロナ禍は、子どもに精神的負荷をもたらしました。
コロナ禍が去っても高止まりの傾向
2023年にはコロナ禍が去りましたが、子どもの自殺が減る傾向はみられません。子どもの自殺では飛び降りや飛び込みといった完遂しやすい方法をとる傾向があり、また、希死念慮から発生までの期間が短いという特徴があります。コロナ禍で対人関係や所属感が希薄化した状態が改善せずに、孤立感を抱いているようです。そして、つらい状態が続くことを悲観し、その状態から抜け出す唯一の解決策が自殺と判断してしまいます。筆者らの調査でも、周囲にSOSを発信していない状況や落ち込んでいることを周囲が確認できない状況で自殺が発生していることがわかりました。
SNSの普及につれて、感情の表出がわかりづらくなったり、周囲に頼ることが少なくなったりすることがみられます。したがって、子どもの自殺を防ぐためには、家庭、地域、学校で何ができるかを検討して複数のセーフティネットが効果的に機能するようにしなければなりません。
筆者ら「滋賀県チャイルド・デス・レビュー(CDR)推進会議」では、子どもの自殺を予防するために、「多方面からの情報を集約して関係者で共有するとともに、県下で複数のセーフティネットを充実させていく」という提言を県知事に手渡しました。子どもの自殺が減らないのは、大人の対応が不十分なのでしょう。特に、医師に課せられる役割は大きいと考えます。