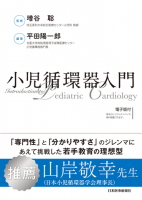お知らせ
感染性心内膜炎(小児)[私の治療]

感染性心内膜炎(infective endocarditis:IE)は,弁膜や心内膜,大血管内膜に細菌が集簇した疣腫を形成する全身性敗血症性疾患である。感染による弁および弁周囲組織の破壊から,弁逆流や弁狭窄を生じ,心不全となるほか,血管塞栓症により多彩な臨床症状がみられる。
IEは,小児では稀な疾患である。しかし,迅速かつ的確に診断して治療を開始しないと,多くの合併症を引き起こして死に至るため,常にIEを鑑別疾患として考慮する必要がある。
▶診断のポイント
小児のIEの発症年齢は,乳児期と思春期に多い。

基礎に心疾患がない小児でもIEを発症することがあり,患者の総数としては心疾患を基礎に有する児よりも多い。微熱や倦怠感を主訴に受診し,不登校などの心因性の疾患を疑われて経過観察され,IEが見逃される症例もしばしば経験する。遷延する発熱,体重減少,抗菌薬の内服で解熱し内服中止で再発熱する経過,新規に出現した心雑音は,IEを強く示唆する。このような症例に出会ったら,心疾患の有無にかかわらず,抗菌薬を漫然と投与することを避け,速やかに適切な検査が行える医療機関に紹介する。
診断には心エコー検査が有用で,疣腫の部位,大きさや形態のほか,弁の損傷や逆流の程度,心囊液貯留などを評価する。また,血液培養を繰り返し採取して,起炎菌の同定に努める。既に抗菌薬が投与されている場合は,抗菌薬を中止して48時間経過後に,血液培養を採取する。
6カ月以内に心臓手術を受けた患者は,IEの発症リスクが高い。疾患の種類では,チアノーゼ性先天性心疾患,完全房室中隔欠損症,大動脈縮窄症や大動脈弁・僧帽弁の弁膜症など,左心系に病変のある患者はリスクが特に高いとされている。
▶私の治療方針・処方の組み立て方
全身状態が安定している場合は,抗菌薬投与よりも起炎菌の同定を優先する。起炎菌が同定されたら,感受性検査の結果に基づき,さらに人工弁の感染かどうかや腎機能障害の有無も考慮し,抗菌薬を選択する。抗菌薬治療は最低でも4週間,多くは6~8週間継続する。
IEにおける心臓手術では,疣腫を含む感染巣の完全な除去と組織の再建(弁形成など)が行われる。手術適応となるのは①抗菌薬抵抗性の感染,②内科治療でコントロール不能な心不全,③塞栓の予防,である。特に10mm大を超える可動性のある疣腫は,塞栓のリスクが高いとされ,抗菌薬投与後数日以内の早期手術が推奨される。

残り1,312文字あります
会員登録頂くことで利用範囲が広がります。 » 会員登録する