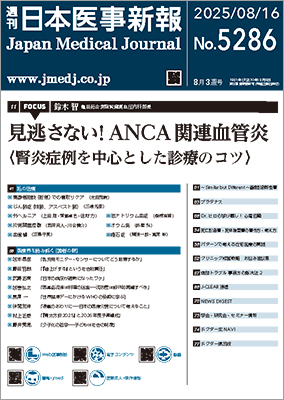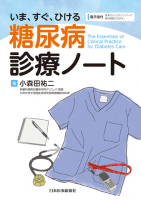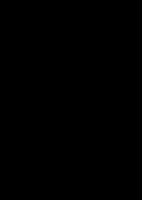お知らせ
■NEWS 【米国糖尿病学会(ADA)】GIP/GLP-1RAとGLP-1RAによる2型DM例CV転帰改善作用を比較:SURPASS-CVOT試験エミュレーション

GIP/GLP-1受容体作動薬(GIP/GLP-1RA)であるチルゼパチドは、2型糖尿病(DM)例の心血管系(CV)イベントを抑制するだろうか―。
意外なことに、この点を1次評価項目に据えた大規模ランダム化比較試験はまだ報告されていない。現在、2型DM 1万3299例をチルゼパチド群とGLP-1受容体作動薬(GLP-1RA)デュラグルチド群にランダム化したSURPASS-CVOT試験で検討中である(臨床試験登録サイト"ClinicalTrials.gov"では2025年6月終了の予定だが、いまだに終了の発表は聞かれない[7月11日時点])。

そこで一足先に、実臨床データを用いてSURPASS-CVOT試験をエミュレーション(模倣)した比較(NCT06779929)が、米国糖尿病学会(ADA)第85回学術集会(6月20日から米国シカゴで開催)にて、ブリガム・アンド・ウィミンズ病院(米国)のJohn W. Ostrominski氏により報告された。
実臨床におけるCV転帰改善に、両剤間で大きな差はないのかもしれない(SURPASS-CVOT試験の主たる目的は、チルゼパチドの「非劣性」証明)。
今回の解析対象は、SURPASS-CVOT試験と同じである。すなわち、アテローム動脈硬化性疾患(ASCVD)既往を有する「BMI≧25kg/m2」の2型DM例で、主たる除外基準は「重度の心不全や腎機能低下」などである。これらに該当するチルゼパチド開始2万2715例とデュラグルチド開始1万1764例を、米国の民間保険会社データベースから抽出し、傾向スコアを用いて125項目の背景因子をマッチできた各群9233例を比較した。
平均年齢は69歳、女性が51%を占めた。なおSURPASS-CVOT試験における平均年齢は64.1歳、女性の割合は28.9%のみだった。さらにHbA1c平均値も、本解析が7.6%だったのに対し、SURPASS-CVOT試験では8.4%という高値だった。一方、高血圧合併率はいずれもおよそ90%、脂質異常症も85%強で、本解析とSURPASS-CVOT試験間に大きな差は認めなかった。
その結果、チルゼパチド群では、本解析における1次評価項目である「総死亡・心筋梗塞・脳卒中」ハザード比が、デュラグルチド群に比べ、0.80(95%CI:0.65-0.99)の有意低値となった。治療必要数(NNT)は、「124/年」である(追跡期間は最長1年間。中央値は5.0カ月)。両群のカプランマイヤー曲線は3カ月後から乖離を始め、9カ月過ぎまで差が開き続けたが、それ以降はほぼ平行だった(12カ月時点での例数はチルゼパチド群:1849例、デュラグルチド群:1078例)。
1次評価項目の内訳を見ると、チルゼパチド群で著明に減少していたのは「総死亡」のみで、心筋梗塞と脳卒中リスクは両群ほぼ同等だった。ちなみにOstrominski氏によれば、チルゼパチド群ではデュラグルチド群に比べ、肺炎や敗血症などの重症感染症の発生率が、有意差には至らぬものの低かったという。
なおSURPASS-CVOT試験における1次評価項目は、本解析と異なり「CV死亡・心筋梗塞・脳卒中」である。今回の解析では「CV死亡」データが入手困難だったため「総死亡」に置き換えたという。
SURPASS-CVOT試験の結果が待たれる。
本研究に対する資金提供については、開示がなかった。