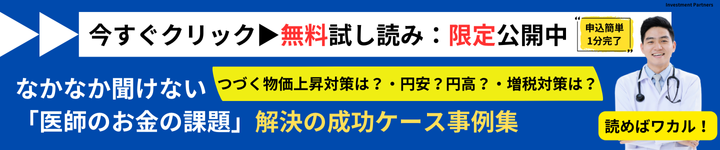お知らせ
シーボルト(7)[連載小説「群星光芒」130]
一行は帰路、佐賀の武雄温泉に宿をとった。入浴の際、高良斎と二宮敬作はシーボルトにうながされて一緒に風呂を浴びた。湯口から豊富な湯がほとばしり、浴槽には透き通った湯が溢れていた。「水晶のように美しい」とシーボルトは感嘆したが、「湯は我慢できぬほど熱い」と顔をしかめた。
良斎はシーボルトの両肩や体幹に多数の傷痕があるのを目にして思い切って訊ねた。
「先生はよほどひどい怪我をなされたのですね」
シーボルトは古傷を摩って緩く笑った。
「若気のいたりでわたしを侮辱した相手に決闘を挑んだのだ」
無事に江戸参府を終えてほっとしたのか、シーボルトは浴室の床台に座りこみ、傷痕の由来をじっくりと語りだした。
「わたしはバイエルンのヴュルツブルクという旧い町で生まれた。父は地元の医科大学教授、叔父たちも同じ大学の外科と産科の教授、2人の従兄もそれぞれ教授を務める医師一族だった。わたしが1歳のとき、父が肺疾で亡くなり叔父の許で育てられた。ヴュルツブルク大学医学部に入学したわたしは同郷会のメナニア団に入団したのだが、団員の1人に、父親の欠けたる者は偏屈だ、と罵られた。わたしは侮辱されたら決して相手を許さない。激しい決闘となり、相手を倒したが、わたしも傷を負い大学病院に担ぎ込まれた。叔父や親族からは“家名を汚した”と手きびしく叱責され、屈辱にまみれた。その後も決闘は32回行った。それからは図書館に閉じ籠って、ツンベリーやケンペルの日本紀行を読みあさった。未知の国ニッポンを目指して新たな出発をしようと決心したのだ」
良斎と敬作は身を固くして聞き入った。
「日本国へ渡る確実な方法はアジア各地に支店を持つオランダ商館の一員となることだ。同社は国籍にこだわらず各国から職員を採用する国際色豊かな会社である。だが医師の場合は軍医の資格が必要だった。さいわい父の門下生がオランダ陸海軍軍医総監の地位にあり、オランダ国王の侍医も務めていた。彼の計らいでオランダ陸軍軍医少佐の資格を得ることができ、オランダの日本商館付き医官に採用されたのだ」。シーボルトは立ちのぼる湯気の中でゆっくりと話しつづけた。
残り1,466文字あります
会員登録頂くことで利用範囲が広がります。 » 会員登録する