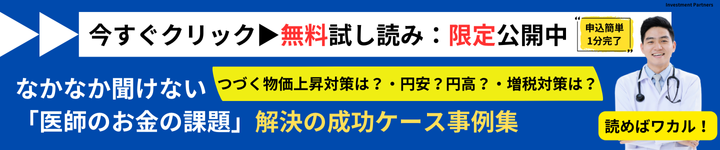お知らせ
土生玄碩(8)[連載小説「群星光芒」147]
浅草の拝領屋敷で暮らす義父はまるで楽隠居のようだった。公方様の許にはときどきご機嫌伺いに参上すれば御用は済む。日頃は三味線や尺八を手にとり贔屓の歌舞伎役者に引幕などを贈って気ままに過ごした。とはいえ生来の好奇心と探求心はいささかも衰えず、ことに新奇の洋薬とあれば手に入れる労を惜しまなかった。
一方、「迎翆堂」の後継者となった土生玄昌はすこぶる忙しかった。西の丸奥医師としての御役目はむろんのこと、医塾の采配と患者の診療、門人の指導育成、医師仲間の会合、その他もろもろの雑事に追われて歳月はまたたくまに打ち過ぎた。
そして文政8(1825)年の暮、久方ぶりに「迎翆堂」を訪れた義父が高揚した口調で玄昌に告げた。
「明春、オランダ甲比丹が公方様の許に参上する。その折、同行する蘭人医師シーボルトが図抜けた名医と評判が高い。ぜひとも面談して西洋眼科の秘伝を訊き出さねばなるまい」
翌くる年の3月4日(陽暦4月10日)、甲比丹スチューレルの一行が蘭人定宿の長崎屋に旅荷をおろした。以来、蘭癖大名とあだ名される薩摩の島津重豪侯をはじめ、蘭方医や蘭学者、本草家らがシーボルト医官に会おうと連日長崎屋へおしかけた。
3月14日、玄昌は義父に促されて本石町3丁目の角にある長崎屋へ出かけた。
旅宿の表通りに白い定紋を染めぬいた緑色の垂れ幕が張り巡らされ、冠木門の前に“おらんだ甲比丹宿”と大書した関札が立つ。 門前に番所を設け、六尺棒を抱えた張り番が四方をにらむ。両脇に大提灯を掲げた門をくぐると御本陣同様の格式ある千鳥破風霧除庇付の表玄関に到着した。
残り1,665文字あります
会員登録頂くことで利用範囲が広がります。 » 会員登録する