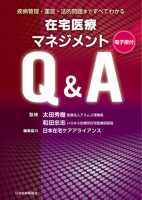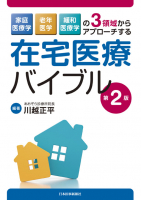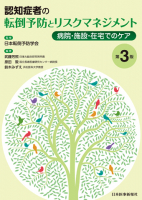お知らせ
フレイル高齢者の予防とケア[私の治療]
▶治療の実際
フレイルの予防および介入には,まずは基礎疾患(生活習慣病,慢性炎症性疾患など)の管理が重要である。そして,サルコペニアも合わせて考えると,適切な運動療法と栄養管理である。運動療法は個人のレベルに合ったものから始めるよう指導する。たとえば,身体機能を維持している人には,定期的なウォーキングやレジスタンス運動も可能であるが,一方で,低い身体機能のケースはベッドの上で足の運動を行うことから始まり,椅子の立ち座りや歩行距離を徐々に延ばしていくなどの工夫をしながら運動強度を調整する。また運動療法に栄養療法(良質な蛋白質やビタミンDなどを十分に摂取)を必ずセットで行う必要がある。低栄養状態で運動を行っても筋肉がつかないどころか,低栄養状態を助長してしまう可能性がある。また,感染症の予防も重要である。
さらに,社会参加の視点も忘れてはならない。継続的に参加できるよう,本人の興味なども聞き出しながら,地域での介護予防教室,通いの場,住民主体の地域活動などにもより積極的に参加できるように促す。
▶多職種連携のポイント
フレイルのリスク因子としては,生活習慣(栄養の偏り・低栄養,運動不足・生活不活発など),各種疾患(生活習慣病,心血管疾患など)や身体的因子(全身の疼痛,難聴,ポリファーマシーなど),心理的因子(抑うつ,意欲低下など),環境因子(配偶者の他界,社会的孤立,孤食など)が挙げられる。フレイルとは社会的側面も含めた多面的な因子が複雑に入り組んだ状態であり,1つの因子だけに着目せず,包括的にとらえて多角的アプローチを施すことが重要である。したがって,よりフレイル状態の悪化が認められるケースにおいては,多職種連携で対応することが求められる。
▶社会資源の活用
基礎疾患への対応のみで管理できるとは限らず,背景に存在する社会的要因なども必ず十分に検討し,地域包括支援センターをはじめ地域資源にしっかりとつなげていくことが必要である。また,地域の高齢者も新しい役割を見つけ,やりがいを感じる「社会の支え手・担い手」となれる新しい地域づくりも求められる。
【制度面への知識】
厚生労働省は令和2年4月から新制度「高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施」を発表し,それに連動してまずは後期高齢者向けの新質問票が作成された3)。いわゆる「フレイル健診」である。今後,全国での後期高齢者健診や地域の通いの場などで使用されることが期待されている。
【文献】
1) 日本老年医学会:フレイルに関する日本老年医学会からのステートメント. 2014.
[https://www.jpn-geriat-soc.or.jp/info/topics/pdf/20140513_01_01.pdf]
2) 国立長寿医療研究センターウェブサイト. 2020.
[https://www.ncgg.go.jp/cgss/department/frail/frail.html]
3) 厚生労働省:後期高齢者の質問票の解説と留意事項. 2020.
[https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/000557576.pdf]
飯島勝矢(東京大学高齢社会総合研究機構・未来ビジョン研究センター教授)