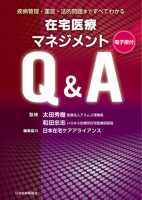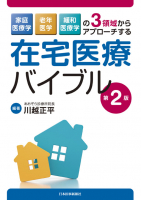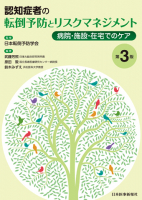お知らせ
高齢者施設(グループホーム)での看取りケア[私の治療]
介護保険法における認知症高齢者グループホーム(グループホーム)の入居条件は,65歳以上で要介護認定が要支援2か要介護1~5であること,医師から認知症の診断を受けていること,施設と同じ市区町村に住所があることなどである。
「認知症対応型共同生活介護」とも呼ばれており,1ユニットが9人までの少人数で共同生活を送るため,家庭的な環境と地域住民との交流のもと,認知症の人であっても穏やかに生活できることを意図した施設である。
認知症高齢者グループホーム,有料老人ホーム(住居型・特定施設),サービス付き高齢者向け住宅は,診療報酬制度上は施設入居時等医学総合管理料の算定が可能であり,居宅系施設「自宅でない在宅」に分類される。
▶管理法と多職種連携
【グループホームにおける看取りケアの実際】
グループホームにおける医療サービスの提供は,協力医療機関,訪問看護ステーションの協力が不可欠なため,まず看取りの対応が可能な医療機関,訪問看護ステーションの選定が重要である。

看取りケアが実施されるには,患者,家族,グループホームの運営者,介護職,協力医療機関の医師,訪問看護ステーションの看護師がカンファレンスなどを通して,方針を共有することが重要である。
看取りケアでは,点滴,喀痰吸引,酸素投与など医療処置が必要となる場合も多く,自宅と同様,ケアマネジャーによる迅速なケアプランの変更が必要となる。
【看取りの取り組みを阻害している要因】
従来グループホームは,認知症の比較的軽い人が,日中はおおむね食堂などで過ごすことを想定した,少ない人員体制で運営されている。
認知症の終末期をケアするケースは少なく,介護職が看取りケアに慣れていない。そのため,入居者の看取りに際して,強いストレスを感じる介護職がいる。
また介護職の医療サービスの提供が制限されており,自宅で家族が介護する場合よりも手間がかかる場合がある。たとえば自宅療養の場合,家族が吸引や経管栄養などの処置を行う場合があるが,介護職がこれらの医療行為を行うためには所定の研修を受けなければならない。さらに自宅療養と比較すると,訪問診療時に家族が同席していることは少なく,意思決定に手間がかかる。

残り979文字あります
会員登録頂くことで利用範囲が広がります。 » 会員登録する