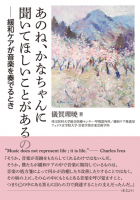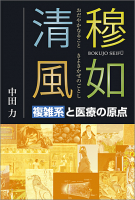お知らせ
報告する努力(志水太郎)[プラタナス]
現在、私のいる獨協医科大学病院総合診療科では、外来、救急、病棟での診療とともに、振り返りをアウトプットすることの重要性をチームで共有している。たとえば、手軽にできる臨床ケースの写真などがその例である。
ある89歳の女性が、10年来の慢性呼吸困難の病歴で受診した。彼女は過去10年間に椎体骨折を起こしたことがあり、最近は咳、痰、胸痛を伴わない呼吸困難が進行していたという。また、身長が低くなり、姿勢の変化が進行していることも家族の話から明らかになった。診察上は、バイタルサインは正常で、肺野の聴診では両側とも清であり、打診も鼓音で左右差なし、心音も正常であった。CTでは胸郭内の明らかな異常所見はなかったものの、顕著な後弯が認められた(写真)。血液検査、心電図、心臓超音波検査の結果、呼吸困難の原因となるような明らかな異常所見は認められなかった。このことから、慢性的な呼吸困難は骨格の変形に伴う機械的な原因によるものと考えられた。


実際にこのケースを振り返ってみた。調べると、高齢者における過後弯症は椎体骨折や椎間板変性症が原因で起こることがあり、このことから気道の歪みで閉塞が生じ、胸郭の可動性が低下することで拘束性換気機能障害を引き起こし、その結果、呼吸困難が生じる、ということが推測された。そのため、後弯への変形をひとまず予防することで、このような呼吸器症状の発生を抑制できる可能性があるだろう、という考察である。
背中の曲がったご高齢の方が息苦しい、いろいろ調べてみたが原因はわからないものの、確かに背中がかなり曲がってるから息が苦しそうだよね、というなんとなくの落としどころでも患者さんへの説明はつかないわけではないが、メカニズムを一歩踏み込んでじっくり文献検索をするとともに考えてみることで、患者さんの納得感や、場合によってはそれについての予防策も得られることになる。
このような思考の轍とプロダクトを残すのには、ケースレポートを書くのが一番である。Peer reviewのある雑誌に書いて、かつ国際的に読まれる英文にすることで、できる限りの多くの人々の目を集めることにつながり、その過程で原稿の洗練度が上がってくるだろう。このような臨床のトレーニングの方法は、「通常の、患者さんを診察する」にプラスした学習効果が得られるということも良い点であると、常々感じる。
【参考】
▶ Shimizu T:Intern Med. 2018;57(15):2281.