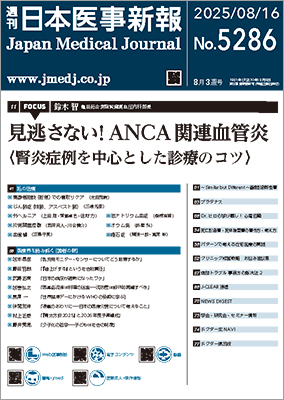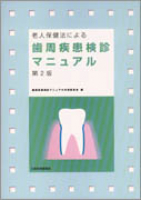お知らせ
顎関節症[私の治療]
顎関節症は,顎関節や咀嚼筋の痛み,関節(雑)音,開口障害あるいは顎運動異常を主要症候とする障害の包括的診断名である1)。身体的,心理社会的要因,習慣的行動要因などの多因子が日常生活上で積み重なり,個体の耐性を超えた場合に発症または悪化する。女性に多く,幅広い年齢層で罹患する。
▶診断のポイント
咀嚼筋痛障害(Ⅰ型),顎関節痛障害(Ⅱ型),顎関節円板障害(Ⅲa型:復位性,Ⅲb型:非復位性),変形性顎関節症(Ⅳ型)の4つに病態分類される。重複罹患者もめずらしくないため,有する病態の的確な診断が重要である。

国際的な診断基準であるDC/TMD1)をもとに診断することが望ましい。鑑別疾患を除外診断するためパノラマX線検査,必要に応じてCT,MRI検査を行う。
▶私の治療方針・処方の組み立て方
【共通の基本治療】
治療は保存的で可逆的かつ証拠に基づく治療法を原則とする1)。まず病態説明と疾患教育を行い,セルフケアの重要性を理解してもらい,意識づけへと誘導することが治療の第一歩となる。個々の習慣的行動要因や精神的要因から生活指導や習癖指導を行い,片咀嚼や上下歯列接触癖などの悪習癖の是正など原因療法に取り組ませて,温罨法や運動療法を習慣的に実施させる。
【Ⅰ型】
局所血流量増加や筋組織の可動化,疼痛緩和のために筋マッサージを行う。また筋スパズムの軽減のために,来院時に経皮的電気刺激療法であるマイオモニターⓇやレーザー療法を併用し,自宅では蒸しタオルなどを用いて温罨法を実施させる。開口制限の緩解のために,運動療法としてゆっくり最大開口させる筋ストレッチを10秒程度/回,1日10回以上繰り返し行うよう指導する。薬物療法は,NSAIDsまたは解熱鎮痛薬を頓用ではなく時間投与で最少量から開始する。アプライアンス療法(口腔内装置の装着による治療)の併用も可能。

残り1,259文字あります
会員登録頂くことで利用範囲が広がります。 » 会員登録する