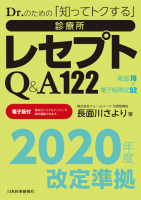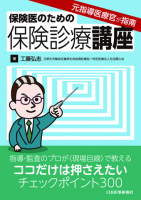お知らせ
■NEWS 26年度改定は物価・賃金などに関する議論から先行開始―中医協総会
中央社会保険医療協議会総会は4月9日、次期2026年度診療報酬改定を巡る議論を開始した。この中で厚生労働省は、物価・賃金の上昇などによって医療機関の経営が過去の改定時以上に厳しい環境下にあることを踏まえ、春から初夏にかけての総会ではまず、医療提供を取り巻く状況や新たな地域医療構想などを含む医療提供体制について議論することを提案、了承された。
7月以降の総会は従来の進め方を踏襲し、7月から9月にかけて改定に関する一巡目の議論、10月以降はより踏み込んだ内容の二巡目の議論を行い、26年2月中の答申を目指す。専門部会や小委員会なども従来通りのスケジュールで進めるが、診療報酬調査専門組織の入院・外来医療等の調査・評価分科会や医療技術評価分科会については、審議経過の報告方法を変更。総会の前に診療報酬基本問題小委員会に報告するプロセスを省き、分科会からダイレクトに総会に報告する仕組みに改める。

総会では診療側、支払側委員がそれぞれ今後の論議に向けた見解を述べた。診療側の長島公之委員(日本医師会常任理事)は、「医療経営が大変厳しい中にあって医療の進歩に対応して国民の医療を守っていくには原資が必要であり、診療報酬による機動的な対応が適時適切に行われる必要がある」との認識を表明。支払側の松本真人委員(健康保険組合連合会理事)は、「保険者は賃金が上がらない状況下でも医療費の水準が上昇し続けていることに強い危機感を覚えている。事務局には医療保険制度の持続可能性の観点からも議論ができるような準備をお願いしたい」と注文をつけた。