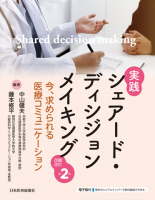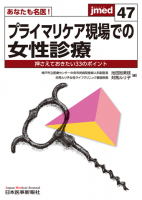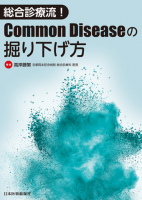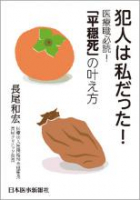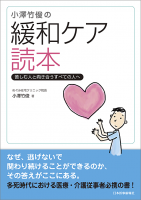お知らせ
【識者の眼】「オープンサイエンスを巡って⑦─オープンアクセスによる研究発信の有効性」船守美穂
前稿(No.5271)では、OA誌に掲載される論文の評価について触れた。本稿では、OA化による研究発信力の強化について論じたい。日本の大学は、世界大学ランキングで順位を徐々に落としつつあり、研究発信力を高めることが急務とされている。
研究発信力は一般に、当該論文が読者に誘発したアクションで計測、評価される。近年は、論文の閲覧数やダウンロード数などもカウントされるが、研究インパクトが伝統的に最も評価されるのは、当該論文が他の研究者の論文において引用された場合である。また、研究活動の多くが公的資金により支えられている現状に鑑み、新聞掲載やSNS、政府文書における論文の引用など、研究が社会に与えたインパクトも評価されつつある。

論文をインターネット上でOAにすると研究発信力が高まるのは、当然に感じられる。OA化された論文の被引用数が、アクセスが制限された論文よりも高いといった分析もあり、OA誌(ゴールドOA)を運営する商業出版社などは、これを、論文のOA出版時に必要となる「論文掲載料(APC)」の正当化に用いている。
一方、機関リポジトリ上で論文原稿を公開するグリーンOAは、どうだろうか? グリーンOAは、ゴールドOAと違い、費用負担なしで論文をOAにできる方法である。しかし、著作権の関係で、正規の「出版版」ではなく、「著者最終稿」と呼ばれる査読を経た採択原稿を公開する。著者最終稿は、未組版、書誌情報なし、さらに、校閲を経るため、文章も出版版と細かい点で異なる場合がある。このため、確実な研究成果として流通させるのには、著者最終稿は不十分との指摘もある。被引用数上昇効果もゴールドOAほどには認められていない。
とはいっても、論文をまったく閲覧できないよりはましである。論文原稿が、不完全ながらもOAとなることで、当該論文の引用や、査読の際の確認が可能となる。これは、積み上げ型の学問において、きわめて重要である。経済的に恵まれない国や機関の研究者が論文を閲覧し、共同研究につながる場合もある。近年は、大量の論文をAIが分析する「メタ研究」も試みられつつある。「出版版」は高額のため、「著者最終稿」の利用に期待がかかる。
OAを世界で初めて定義したブダペスト・オープンアクセス・イニシアティヴ(BOAI)では、OAを「財政的、法的また技術的障壁なしに、誰でも論文を無料で、閲覧、ダウンロード、コピー、配布、印刷、検索、(略)などができること」と定義し、論文にアクセスする際のあらゆる障壁と利活用の方法を視野に入れている。日本ではOA論文を「無料で閲覧できる論文」と理解している場合が多いが、「OA」は範囲がより広く、大きい。
人類の知見は、他者の知見の上に新たな知見を積み上げることで発展する。論文をOAにすることにより、研究者と社会の人々が協力して、学術と社会の発展に寄与できるとよい。
船守美穂(国立情報学研究所情報社会相関研究系准教授、鹿児島大学附属図書館オープンサイエンス研究開発部門特任教授〔クロアポ〕)[論文のOA化][研究発信力][研究評価]