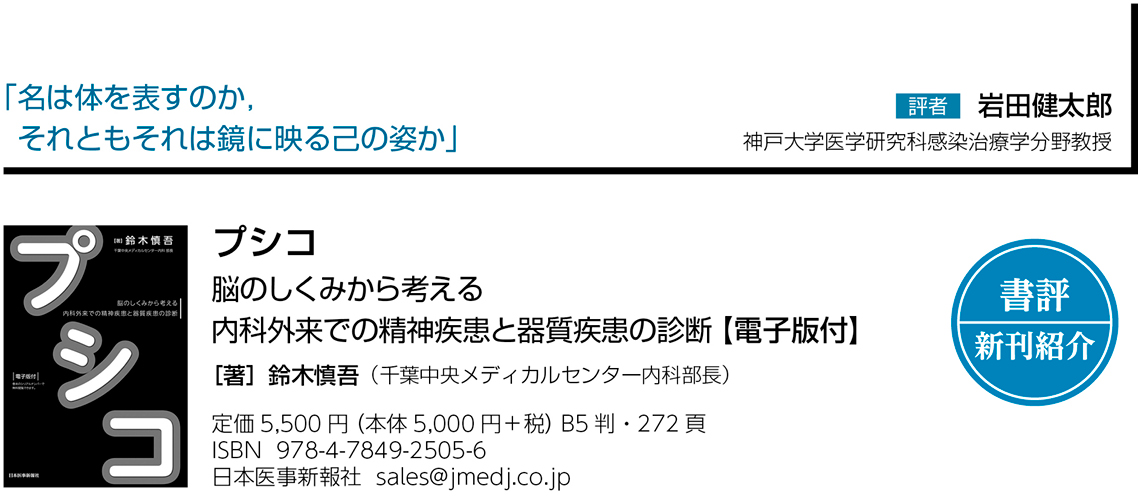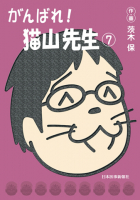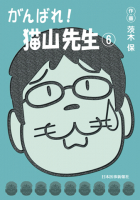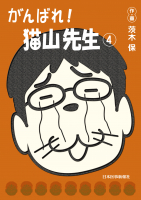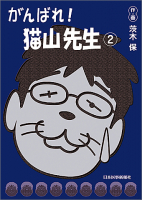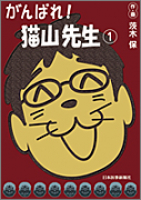お知らせ
【書評】『プシコ 脳のしくみから考える内科外来での精神疾患と器質疾患の診断』名は体を表すのか,それともそれは鏡に映る己の姿か
『プシコ 脳のしくみから考える 内科外来での精神疾患と器質疾患の診断』が本書のタイトルだ。が,最初の「プシコ」だけみて「ん?」となる読者は多いだろう。私も一瞬,「ん?」となった。
これが,仕掛けである。
本書「まえがき」にもあるように,本来は古代ギリシャ語の「霊魂」を意味する普通のニュートラルな言葉である。しかし,医療者の多くはこの言葉をあるカテゴリーの患者グループを指す総称として用い,ときどき(しばしば)そこには侮蔑のニュアンスが込められる。そのニュアンスを敏感に感じ取ってしまう己の中にも,そういうバイアスが潜んでいないか。
私達は本書に試されているのである。
私が生まれた島根県で,人が「部落」というときは,市町村よりも小さな地域という意味でしかなく,そこには差別的なニュアンスはない。私が現在住む近畿地方のような,暗喩は込められていない。もちろん,神戸で私はこのような言葉を使うときは慎重になるだろう。しかし,島根県内で人々が「部落」の話をしているときに,よそから入ってきた人が我々を論難するのは的外れだ。本質と形式がとっ散らかっているのである。日本でよく見る光景ではあるが。
で,忘れがちなのだがタイトルだ。よく読めば本書は「内科外来」の本なのである。内科外来に密かに入り込む「プシコ」の世界。本書に出てくる疾患や病態の殆どは,私達が内科領域で経験するものだ。「プシコ」の世界と「ソマ(肉体)」の世界には連続性があり,しばしば同居,あるいは相互作用を起こしている。内科外来から「プシコ」を切り離して患者を診るのは不可能だし,不合理でもある。しかし,私達は高血圧やCKDのようにすっきりと「プシコ」の世界をタビュレートできない。だから,「プシコ」の一言に逃げてしまい,ときに精神科医に丸投げしてしまうのだ。
それではもったいなさすぎる。内科外来の一番面白いところが失われてしまう,と極言したってよい。
慢性骨盤痛症候群や機能性高体温症,身体症状症,パーソナリティ症などは内科外来の(あるいは救急外来の)コモンディジーズだ。自分の中でアルゴリズムを作り,テキパキと診断,対応できるととても嬉しい。その時,「プシコ」という奇妙な用語(あるいはカテゴリー)は消失する。このアウフヘーベンこそ,本書の読後に得られるカタルシスなのだ。診断に興味のある内科医は……診断に興味のない内科医が形容矛盾なのだと信じたい……必読である。