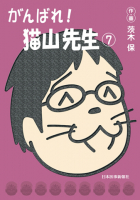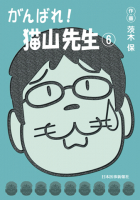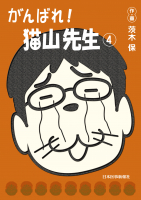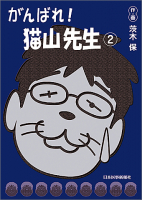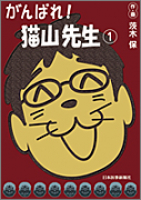お知らせ
専門家に聞く!医師のための終活入門 人生の最終章に「遺贈寄付」という社会貢献を[日本医事新報特別企画:ライフスタイル特集「彩りのあるシニアライフを送る 医師の終活」]
長く働き続けられる「医師」という職業だからこそ、早くからしっかりと自分の理想のシニア生活に合った働き方や閉院・終活を考える必要があります。
長寿化が進展し、生き方が多様化した現代は、自分自身の終活だけでなく、医院・クリニックの終活、ご家族の終活など、備える範囲は多岐に渡るでしょう。
今回は先生方の終活の支えになるサービス・企業をご紹介!「理想のシニア生活」を送るためのヒントになる情報をまとめました。ご自身だけでなく、ご家族の終活を考える先生方もぜひご活用ください。
(日本医事新報特別企画・ライフスタイル特集「彩りのあるシニアライフを送る 医師の終活2025」の全文はこちらから無料でダウンロードできます)

一般社団法人全国レガシーギフト協会 共同代表 山北 洋二さん
大学時代の募金活動をきっかけに交通遺児育英会へ入職、あしなが育英会初代事務局長として遺児支援に尽力した。近年は遺贈寄付をさらに社会に広めるために活動している。
■終活とは「自分らしい最期」を準備すること
「終活は、自分の人生を振り返り、最期をどう迎えたいかを考える機会です。遺贈寄付はその一部であり、自分のお金を最後にどう使うかという意思を形にするものだと思います」と山北さんは語ります。
終活の第一歩として、財産目録の作成が挙げられます。預貯金、不動産、有価証券だけでなく、住宅ローンなどの負債も含めて一覧にしておくことが大切です。また、遺言書の作成も重要な準備のひとつ。法的効力のある公正証書遺言や、気軽に始められるエンディングノートなど、状況に応じた選択が可能です。
「エンディングノートには、医療や介護に関する希望、友人の連絡先、パスワードの一覧など、亡くなった後に家族が困らないようにする情報をまとめておくと良いですね。“エンディングファイル”という形で、保険証券や登記簿のコピーなどをまとめて整理しておくやり方もおすすめです」
延命治療や尊厳死、臓器移植などに関する意思表示も、認知症などで判断力が低下する前の元気なうちに家族と話し合っておくことが望ましいでしょう。
■社会貢献と税制メリットを両立する選択肢
遺贈寄付とは、残された財産を遺言によってNPO法人や公益法人、教育機関、地方自治体などに寄付することです。生前に使いきれなかったお金を、社会のために役立てる“人生最後の社会貢献”とも言えます。
最も一般的なのは、遺言書に寄付の意思を記す「遺言による寄付」です。故人の意思が最大限に尊重され、法定相続人以外の団体や個人にも財産を遺すことが可能になります。一方、相続人が相続財産の一部を寄付する「相続財産からの寄付」もあります。遺言がなくても相続人自身の判断で寄付を行うもので、寄付先やタイミングによっては相続税の非課税措置や寄付金控除が適用される場合もあります。信託による寄付や死因贈与契約、生命保険による寄付なども可能です。
「財産の一部を指定する“特定遺贈”や、割合で指定する“包括遺贈”など、寄付の仕方にも選択肢があります。ただし、包括遺贈の場合は連帯保証債務や借金などの負債も引き継ぐ可能性があるため、事前に寄付先と相談しておくことが大切です」
■少額からでも始められる「最後の社会貢献」
遺贈寄付は、数万円から数億円まで幅広い金額で行われており、少額でも十分に意義があります。団体によっては、感謝状や活動報告が届くこともあり、残された遺族へ温かい想いを残せる場合があります。
長年の経験から山北さんは「遺贈寄付を決めたことで、人生の区切りがついたとおっしゃる方も多くいらっしゃいます。自分の意思でお金の行方を決められることが、精神的な安心につながります」と語ります。
医師として社会に貢献されてきた方々にとって、遺贈寄付はその歩みを社会へと引き継ぐ、自分らしい生き方の締めくくりとなる選択肢といえるでしょう。人生の最終章にぜひ「寄付」という社会貢献を検討していただきたいと思います。
▶遺贈寄付を考える際の注意ポイント◀
①遺留分への配慮
遺贈寄付によって法定相続人の遺留分を侵害すると、相続トラブルにつながる可能性があります。事前に専門家へ相談し、配慮した内容にすることが大切です。
②遺言書の形式と作成方法
自筆証書遺言は形式不備で無効になるリスクがあります。確実に意思を残すためには、公正証書遺言など、専門家が関与する方法の検討がおすすめです。
③寄付先の団体の確認
税制優遇を受けるには、寄付先が国の要件を満たしている必要があるため、寄付先の受け入れ体制や条件を事前に確認しておくことが重要です。
活動内容や寄付金の使途が、自身の社会貢献の意図と合致しているかも、事前に見極めておくと安心です。