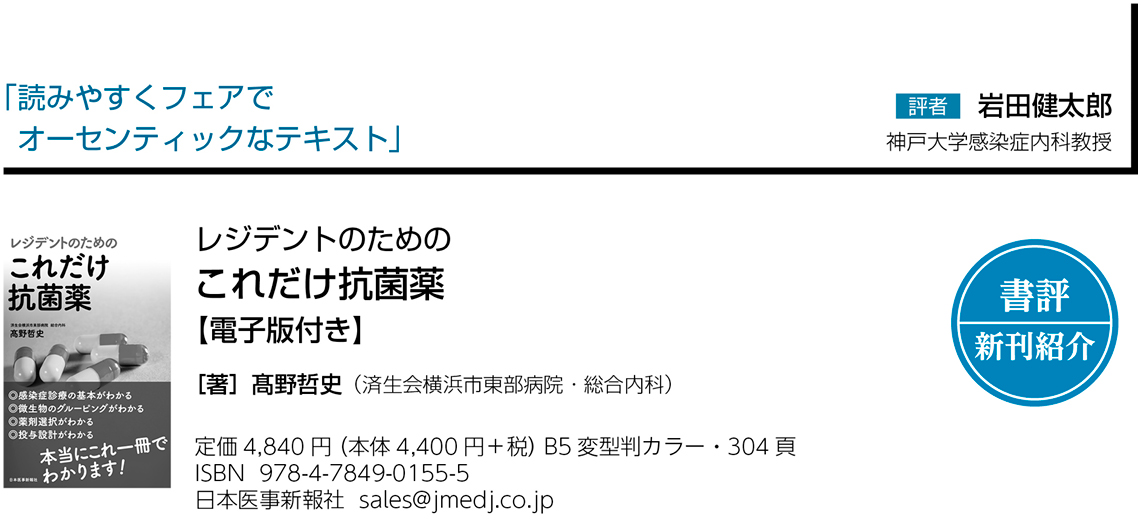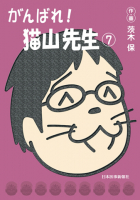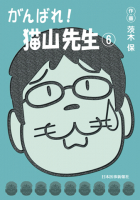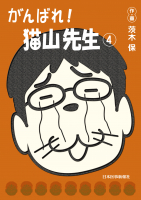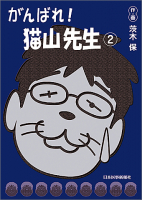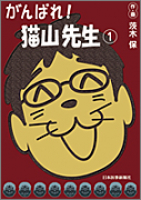お知らせ
【書評】『レジデントのためのこれだけ抗菌薬』読みやすくフェアでオーセンティックなテキスト
ダニング・クルーガー効果と呼ばれる現象がある。ビギナーのときには自身を過大評価しがちで,経験と鍛錬を重ねるうちにその自信は減っていく。その後ゆっくりと能力と自信がシンクロして立ち上がっていく,というものだ。この現象の普遍性については学問的には賛否あるようだが,仮に普遍的ではないにしてもこういう現象自体はしばしば観察する。
本書は切れ味のよい断言口調で,読みやすい。しかし,それはビギナーのときに覚えた「ハウツー」を連呼しているのではない。「細かいことはクドクド,いろいろあるんだけど,まずはとりあえず捨象しておきましょうね」という断言口調だ。本書の想定読者は医学生や研修医だろうから,「あ,これでわかった」とスッキリするだろう。ちょっと勉強した後期研修医ならば,「でも,あのこととかこのこととか書いてないじゃないか」と重箱の隅をつつきたくなるかもしれない。ちょっと勘違いしたベテランドクターなら,「文章がわかりやすすぎて威厳が足りない」と見当違いな文句を言う可能性すらある。慧眼を持つ読者ならば,「ああ,著者はわかっていてあえてシンプルに書いているんだな」と見抜くだろう。ネットの時代にコンテンツを膨らませ続けるのは容易なのだ。難しいのは,何を割愛するか,だ。
どの領域でもそうだと思うが,感染症診療においても大切なのは情報ではなく,原則だ。本書の端々にその原則がピシッと筋を通しているのがわかり,著者がオーセンティックな感染症のトレーニングを受けてきたことが伺われる。各医薬品に対する態度もフェアで,ともすれば散見されやすい「利益相反的なエコヒイキ」もみられない。
抗菌薬は当該微生物に対する効果だけでは評価できず,そこにはエビデンスも必要だし,他の薬との相対評価も必要だ(今,薬の説明会で禁止されてる,あれである。相対評価ができなければ薬を使うことは不可能なのに,ね)。そこもしっかりしているので本書は安心して読める。なぜ,バンコマイシンがファーストラインで,ダプトマイシンはセカンドなのか。なぜ,イトラコナゾールやポサコナゾールは,その薬効にもかかわらずポジショニングで不利なのか。原則がしっかりと説明されている。
医学生や研修医が読むべきは,読みやすいけれどもフェアでオーセンティックなテキストだ。本書はまさにそういう一冊だ。惜しむらくは表紙である。私は面食いなので,装丁はモダンにしてほしかった。