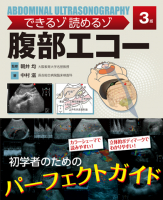お知らせ
肝外胆管癌[私の治療]

肝外胆管癌は肝外胆管に発生する悪性腫瘍の総称で,50歳代から少しずつ増えはじめ,70歳代以降に多くみられる。胆管閉塞に伴う黄疸や肝障害,胆汁感染に伴う胆管炎などの病態を引き起こす。局在により主たる外科切除術式が異なり,肝門部領域胆管癌と遠位胆管癌に大別される。
▶診断のポイント
【症状】
黄疸(閉塞性黄疸)関連症状で発症することがほとんどであり,皮膚や眼球結膜の黄染,褐色尿,灰白色便,瘙痒感などが典型的な症状である。時に胆管炎の症状として,悪寒・発熱を伴うことがある。

【血液・画像検査】
黄疸が顕在化する前にALPやγ-GTPなどの胆道系酵素の上昇をみることがあり,黄疸を伴うと間接型優位のビリルビン値の上昇を伴う。腹部超音波検査は簡便で,肝内胆管の拡張が観察される。dynamic CT(Dy-CT)やMRI(MRCP)は特に有用であり,胆管狭窄部の描出や腫瘤像・壁肥厚像がとらえられ,局在診断のみならず進展度診断も可能である。多くの場合,胆道ドレナージを,原則,内視鏡的に行うため,直接胆道造影やIDUS,EUSを用いた診断がなされる。
【病理学的検査】
胆汁細胞診や擦過細胞診,生検によって病理学的診断を行うが,必ずしも感度は高くない。

残り1,964文字あります
会員登録頂くことで利用範囲が広がります。 » 会員登録する