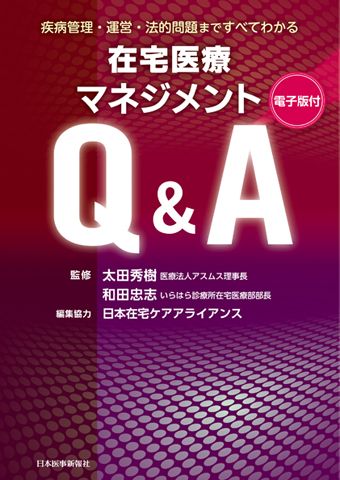お知らせ
超高齢社会に対応した「理想の内科医」とは?―内科医の9割、臓器横断的診療を「実践」【内科学会特別シンポ】
超高齢化の時代に対応した内科医の姿とは――? 15日に都内で開かれた日本内科学会講演会の特別シンポジウムで、さまざまな立場で働く医師が「理想の内科医像」に対する見解を語った。シンポでは、臓器横断的な診療姿勢を有し、実践に努めている内科医が9割に上るとの調査結果も公表された。
同学会は3月、超高齢社会で同学会が果たすべき役割と責任について、「ひとりひとりの生活の質に配慮し、全身を診る、臓器横断的な診断治療を行える内科医」の育成に努めるとする宣言を発表した。これが同学会としての「理想の内科医像」とも言えるが、内科医の働く環境によって理想像は異なってくる。

■都市部「大半の症例の入口は内科医でいい」
シンポで都市部の総合病院の視点から講演した有岡宏子氏(聖路加国際病院)は、「大半の症例は内科医が“入口”でいい」とし、「任せるべき症例をきちんと判断するためにも、普段から専門医と密な連携をとるべき」と指摘。一方、山邊裕氏(市立加西病院)は地方の市中病院の立場から、サブスペシャルティを持つ専門医にも一般内科医として働いてもらうことで「病院の診療を回せる」としつつ、「各医師の専門性の担保が課題だ」と話した。
在宅医療に注力する開業医の川越正平氏(あおぞら診療所)は、「地域を1つの病棟として捉える意識が必要」とした上で、地域医療や多職種連携について学ぶ機会を卒前・卒後ともに十分確保すべきとの考えを示した。大学病院や医学教育の立場からは、佐々木裕氏(熊本大)が「今後の内科医はGeneralityをいかに広げられるかがポイントとなる」と強調。松村正巳氏(自治医大)は「specialtyとgeneralityは対立概念ではない」とし、「医学生のうちから総合診療マインドを持ってもらう教育が重要ではないか」と述べた。

残り425文字あります
会員登録頂くことで利用範囲が広がります。 » 会員登録する