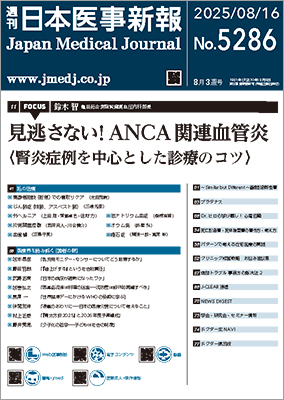お知らせ
■NEWS かかりつけ医の心疾患診療などでシンポ―日本学術会議

日本学術会議は21日、心疾患の診療提供体制をテーマとしたシンポジウムを都内で開催した。かかりつけ医による心疾患診療や多職種連携、心臓リハビリテーションの定着などについて活発な討論が行われた。
シンポは、循環器病対策基本法が昨年制定したことを受けたもの。冒頭で日本医師会常任理事の羽鳥裕氏は、「医師会として多職種・多機関と連携して一層の対策に取り組む」と意欲を見せた。

■労働人口の減少を踏まえ、「地域で効率的に診る必要」
シンポでは、在宅医療を行っている立場から弓野大氏(ゆみのハートクリニック)が「(日本の社会問題として)少子超高齢化もあるが、さらに重要なのは労働人口の減少だ」と指摘。「地域では専門スタッフがほとんどいない前提で医療を行う必要がある。いかに地域でコンパクトに、効率的に診るかがポイントだ」と述べた。その上で弓野氏は、「私たちの地域で、専門医療機関から送られてきた情報提供書100例をみたところ、心肺運動負荷試験(CPX)の結果や心臓MRIなどの結果が細かく書いてある一方で、非専門医が心不全患者を診るための有効な指標である体重の記載は14%しかなかった」と問題視。専門医療機関から地域へスムーズに患者を受け渡すことが、地域の医療体制構築につながるとした。
これについて広島大学副学長の木原康樹氏は、「基幹病院と地域にいるかかりつけ医のコミュニケーションは希薄だ」と述べ、地域の医師が求めている情報と専門医療機関からの情報提供書の記載内容には「大きなギャップがある」と課題を共有した。
■心リハの普及、急性期病院からの円滑な流れの整備を
日本心臓リハビリテーション学会理事長の牧田茂氏は、日本医療研究開発機構(AMED)の研究班が2017年に発表した心不全患者の心リハの実施率の調査結果を紹介。5万1323人のデータのうち、入院中に心リハが実施されていたのは32.7%、入院・外来両方では7.3%に留まっていたとして問題視した。牧田氏は、心リハの普及に向け、急性期病院で病態を層別化した上で、適切な心リハにつなげる円滑な流れの整備や認定施設数の増加、医療者の理解などを求めた。

地域での心疾患診療について、労働人口減少を踏まえ効率化する必要性を指摘した弓野氏(右)