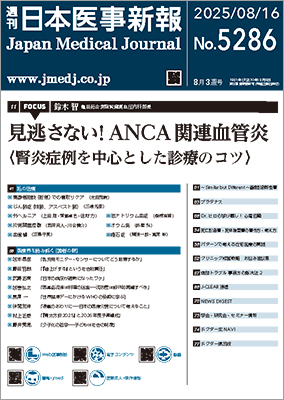お知らせ
高血圧性脳症[私の治療]

高血圧性脳症は,急激で重度な血圧上昇後に脳浮腫を生じ,急性または急速進行性の意識障害や局所神経症状を伴う。神経症状に血圧上昇を伴うことが多い疾患,特に脳梗塞や脳出血などを速やかに除外することが重要である。治療は降圧療法が中心である。本稿では,高血圧性脳症と関連する後部可逆性脳症症候群(posterior reversible encephalopathy syndrome:PRES)1)について主に述べる。
▶診断のポイント
PRESは患者背景,症状,経過,画像所見に特徴がある。

【診断基準】
確立されていない。患者背景,臨床症状,画像診断を組み合わせて行う。
【除外が必要な他疾患】
脳梗塞,脳出血,脳炎,腫瘍性病変,中枢神経血管炎,進行性多巣性白質脳症,浸透圧性脱髄症候群,急性散在性脳脊髄炎,中毒性白質脳症など。
【患者背景】
急激な血圧上昇,腎機能障害,細胞障害性薬剤,抗癌剤,免疫抑制薬,自己免疫性疾患,子癇前症,子癇,敗血症を背景として発症する2)。
【臨床症状】
特異的な症状はない。意識障害,痙攣,頭痛,視覚障害,片麻痺,失語などが急速に出現する2)。
【臨床経過】
急性発症のことが多いが,数時間~数日のうちに症状が顕在化する急速進行性のことがある。適切な治療により,75~90%の症例は可逆性である2)。著明な脳浮腫や脳出血を合併した場合や,原因疾患のコントロールまで時間を要した場合は非可逆的となることがある2)。
【画像所見】
後頭~頭頂部に血管原性浮腫を呈することが多い。MRIが有用で,FLAIR画像やT2強調画像で高信号になり,その部分はapparent diffusion coefficient(ADC)値が上昇し,拡散強調画像では等~低信号になる。病巣は両側性のことが多く,通常は可逆性である。病巣は前頭葉,側頭葉,小脳に及ぶことがある。病巣が「完全に一側性」「脳幹のみ」「小脳のみ」の場合は他疾患を鑑別する必要がある。脳血管攣縮を伴うこともある。
▶私の治療方針・処方の組み立て方
速やかに脳梗塞や脳出血など他疾患をCT,MRIで除外し,血圧など全身状態をモニタリングできる集中治療室やそれに準じた環境で入院精査加療を行う。血圧管理を開始し,上述した疾患の鑑別診断を行う。過度な血圧変動を避ける観点から,薬剤は経口薬よりも非経口薬が好ましい。降圧薬の種類による有効性の違いがあるかどうかは不明である。わが国ではニカルジピン点滴静注による管理が一般的と考える。

残り1,164文字あります
会員登録頂くことで利用範囲が広がります。 » 会員登録する