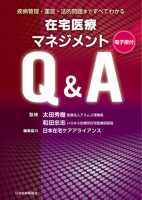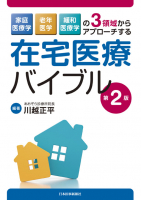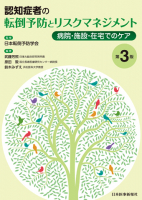お知らせ
慢性心不全[私の治療]
▶治療の考え方
心不全治療薬においては,予後改善薬と症状緩和薬に大別される。拡張不全には予後改善薬のエビデンスはまだ不十分であり,利尿薬や併存症を中心とした治療になる。収縮不全には予後改善薬としてACEI(ARB/ARNI),β遮断薬,MRA,SGLT2阻害薬の4剤が挙げられるが,在宅の超高齢者でカヘキシーが進行し,血圧低値,腎機能低下などの背景を持つハイリスク症例においては,それぞれの臨床背景をみながら減薬も考えていく。利尿薬の使用においては,ループ利尿薬,スピロノラクトン,バソプレシン受容体拮抗薬,サイアザイド系利尿薬を組み合わせていく。具体的には,うっ血管理のために,スピロノラクトンとバソプレシン受容体拮抗薬の両剤のdoseを意識しながら有効活用する。
▶治療の実際
88歳男性。左室駆出率30%,収縮期血圧80mmHg,eGFR 30mL/分/1.73m2にて徐々に血圧低下,腎機能悪化を認める。このような症例では,うっ血がなければ利尿薬を減量,中止とし,ACEI/ARB/ARNIを減量,中止する。脈拍が60bpm以下になってくるときは,β遮断薬の減量を考える。

鎮静については,患者の苦痛緩和を行う最終手段であり,生命予後の短縮のために行うわけではないこと,また意思疎通がとれなくなる可能性についても患者家族に説明することが大切である。在宅の現場では,ベンゾジアゼピン系坐薬〔ブロマゼパム「サンド」(ブロマゼパム),ダイアップⓇ(ジアゼパム),ワコビタールⓇ(フェノバルビタールナトリウム)〕が頻用される。
▶介護者・家族への助言
一般的な心不全のステージ,MAGGICスコアなどを用いた予後予測は客観的指標となりえるため有効である。予後の伝え方は,診療のたびに「悪い,悪い」は禁句であり,「最善を期待しながら,最悪に備える」ことを伝える。
例:「心臓病を抱えながらも長生きすることを期待しています。しかし,思ったよりその時間が短いかもしれないということも心配しています」
▶多職種連携のポイント
在宅では非専門スタッフがほとんどであり,専門医療機関と違い,職種間での疾患に対する知識の差が,患者のとらえ方に相違を生じさせる。心不全増悪をより早期に発見するために,「心不全増悪時の症状の出方」「至適体重の設定」「至適BNP/NT-proBNP値」は,非専門で構成されるチームにとって簡便な指標となる。
心不全は慢性疾患で病状が変化しやすいのが特徴であり,病期,治療ケアの方針など,施設間でのコミュニケーション,情報共有のため,「退院前カンファレンス」「担当者会議」「入院前カンファレンス」として,オンライン会議を上手に利用しながら話し合いの場を設ける。
地域での非専門の医療介護職のスタッフは,循環器疾患に対して不安を抱えながら過ごしている。筆者らは,地域で循環器疾患,心不全で問題を抱える医師や看護師,リハビリテーションスタッフなどの医療従事者が集まるプラットフォーム「ハートケアステーション」を運営している。完全非公開型医療介護専用SNS〔MedicalCareStation(メディカルケアステーション)〕を用いて,循環器疾患に携わる医療従事者がワンストップでつながる,無料でのコンサルティングシステムを構築している。
弓野 大(医療法人社団ゆみの理事長)