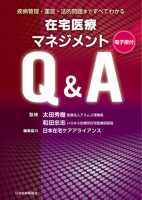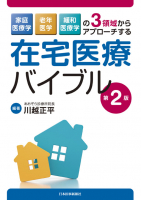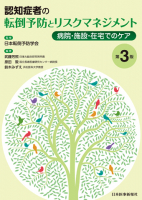お知らせ
せん妄への対応[私の治療]
がん患者のせん妄有病率は高く,進行がん患者では26~62%,終末期患者では88%以上に発生するとされる1)2)。一般的に,せん妄に対しては原因となる病態への介入や環境調整などの非薬物的アプローチが第一選択となるが,本稿では,看取りが近いがん患者の終末期せん妄への対応を中心に述べる。
終末期せん妄の原因は複数かつ不可逆的であることが多いため,実臨床では薬物療法が必要となる場合が多い。終末期せん妄は,患者の身体的,心理社会的に大きな負担となる苦痛のひとつで,患者とその介護者の双方に重大な影響を及ぼす可能性がある3)が,在宅医療ならではの視点として,終末期せん妄を「お迎え現象」としてとらえ,家族に説明する場合もある。
▶状態の把握・アセスメント
【せん妄の評価】
在宅ではCAM(confusion assessment method)が使用しやすい。

①急性発症で状態が変動する〔例:短期間(通常数時間~数日)で出現/日内変動があり,症状にむらがある〕
②注意力の欠如(例:話していてもすぐに患者の気が散って違うことをしようとする/こちらの質問を覚えていられない)
③考えがまとまらない,的外れな会話(例:話のつじつまが合わない/内容がまとまらず,何を伝えたいのかわかりにくい)
④意識レベルの変化(例:傾眠傾向/活気がありすぎる)
①と②を満たし,③か④のどちらかが該当すればせん妄の可能性が高いと言える。
【せん妄の原因の評価】
直接因子(薬剤,感染症,低酸素など),促進因子(痛み,便秘,不眠など)に可能な範囲で対応する。
▶アセスメントのポイント
「現在のせん妄状態が続いた場合に家族が対応できるか」という視点で評価し,薬物治療や療養環境について検討する。

残り1,270文字あります
会員登録頂くことで利用範囲が広がります。 » 会員登録する