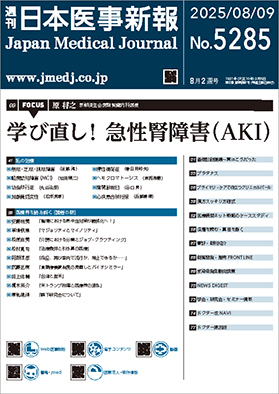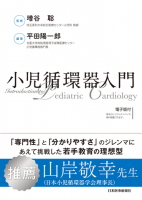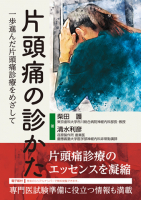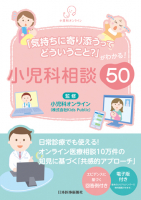お知らせ
亜急性硬化性全脳炎(SSPE)[私の治療]

亜急性硬化性全脳炎(subacute sclerosing panencephalitis:SSPE)は,麻疹罹患後に数年~十数年の潜伏期間を経て発症する亜急性進行性の稀な遅発性感染症である。何らかの宿主要因,麻疹ウイルスの変異を基盤として,脳内持続感染と伝播を経て,多くは小児期から思春期にかけて発症する。わが国の発生率は全年齢人口100万当たり年間0.3人で,麻疹患者約8000人当たり1人発症するとされている。
▶診断のポイント
【症状】
初期は性格変化,学業不振等の軽微かつ非特異的な症状であるため見逃されやすい。ついで,特徴的なミオクローヌスが出現し,診断の契機となる。筋緊張亢進,錐体外路症状が進行して寝たきりとなり,自律神経症状(異常な発汗,不規則な発熱,分泌物の増加),意識障害,呼吸障害等が現れる。

【検査所見】
症状,経過から疑い,脳脊髄液検査で麻疹抗体価の上昇を認めれば診断に至る。脳波では初期から周期性同期性放電を認め,診断の助けとなる。MRIは非特異的であり,初期は異常を認めないことがある。その他,髄液オリゴクローナルバンド陽性,IgG index高値になることが多いが,髄液ではPCR法を用いても麻疹ウイルスは通常検出されないため,注意が必要である。
▶私の治療方針・処方の組み立て方
現時点でエビデンスの高い根治療法はない。免疫調整効果を有する抗ウイルス薬であるイノシン プラノベクス(改善もしくは進行抑制率11~66%),非特異的な抗ウイルス作用を有する免疫調整薬であるインターフェロン(改善率17~50%,進行停止率22~28%),RNAウイルスに対する抗ウイルス作用を持つリバビリン(改善率70%)等が進行を遅らせる可能性がある。
【治療上の一般的注意&禁忌】
わが国で保険適用のある治療(2023年10月時点)は,イノシン プラノベクス内服とインターフェロンαの脳室内投与のみである。インターフェロンは血液脳関門を通過しにくいため,Ommayaリザーバーを留置した上で髄腔内投与が行われる。リバビリンは研究段階の治療で,ウイルス増殖を完全に抑制する髄液濃度50~200μg/mLを目標として投与するとされているが,経口では目標濃度に到達せず無効であったため,脳室内投与が試みられている(2017年に検査会社の受託は中止となっている)。副作用は,イノシン プラノベクスでは血中および尿中尿酸増加と嘔気がみられる。インターフェロンでは発熱がほぼ必発で,無菌性髄膜炎等もみられ,リバビリンでは口唇腫脹,頭痛,眠気が知られている。

残り929文字あります
会員登録頂くことで利用範囲が広がります。 » 会員登録する