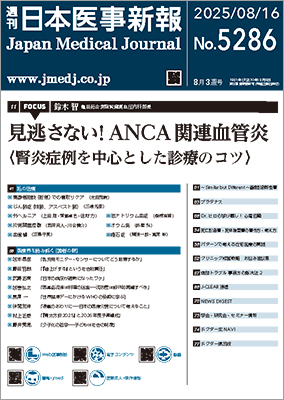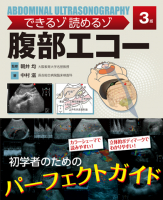お知らせ
B型肝炎[私の治療]

B型肝炎ウイルス(hepatitis B virus:HBV)の感染は,持続感染と一過性感染に大きく分類できる。持続感染は,主に出産時の産道感染による母子感染,幼少期の集団予防接種(現在は改善されている),家族間感染などにより成立する。近年ではワクチン接種などの様々な対策により,母子感染をはじめとする幼少期の感染が予防できるようになったため,若年者のHBs抗原陽性率は急速に低下し,持続感染は高齢者を中心に認められる。一過性感染は,成人の性行為感染が原因となることが多く,重症になると急性肝不全などにより生命に危険が及ぶことがあるが,多くの症例では治癒後に血液中のHBVは検出感度以下になる。しかし,遺伝子型AのB型急性肝炎では7~8%の症例で持続感染に移行する1)。
▶診断のポイント
成人の初診患者で,HBs抗原が陽性でASTおよびALTの顕著な上昇を伴う場合,HBVの初期感染による急性肝炎か持続感染からの急性増悪であるか迷う症例が少なからず存在する。その場合には,HBs抗原だけではなくIgM-HBc抗体および(IgG-)HBc抗体を測定し,IgM-HBc抗体が高値であれば初期感染による急性肝炎,HBc抗体が高値であれば持続感染からの急性増悪であるとの診断が可能である。

また,免疫抑制・化学療法中もしくは終了後で,過去にHBs抗原陽性,もしくはHBc抗体かHBs抗体が陽性,もしくは両方陽性であることが指摘されていた場合には,B型肝炎のキャリアもしくは既往感染からの再活性化の可能性がある。
▶私の治療方針・処方の組み立て方
現在,B型肝炎に対して使用できる薬剤は,ペガシスⓇ(ペグインターフェロン アルファ-2a)と核酸アナログ製剤である。核酸アナログ製剤には,ラミブジン(LAM),アデホビル(ADV),エンテカビル(ETV),テノホビル ジソプロキシルフマル酸(TDF),およびテノホビル アラフェナミドフマル酸塩(TAF)があるが,ADVは2022年5月に販売中止となった。また,LAMは耐性出現率が高く,現在では第一選択の治療薬とはならない2)。
B型急性肝炎に対しては,対症療法のみで基本的には抗ウイルス療法の適応にはならないが,急性肝不全への移行や遺伝子型Aにより慢性化が危惧される場合には,早期より核酸アナログ製剤を投与する。急性肝不全(発症から8週以内に,PT 40%以下もしくはPT-INR 1.5以上)では,急性感染かキャリアからの急性増悪かにかかわらず,可及的速やかに核酸アナログ製剤による治療を開始する。
B型慢性肝炎の治療対象は,HBe抗原の陽性・陰性にかかわらず,ALT 31U/L以上かつHBV DNA量2000IU/mL(3.3LogIU/mL)以上である。また,肝硬変ではHBV DNAが陽性であれば,HBe抗原,ALT値,HBV DNA量にかかわらず治療対象となる。B型慢性肝炎における治療の長期目標は,HBs抗原の消失である。治療方針として,HBs抗原消失をめざすためにペグインターフェロン治療を第一に検討するが,実際にはHBe抗原セロコンバージョン率やHBV DNA陰性化率が必ずしも高くないこと,治療前の効果予測が困難であること,予想される副作用,などにより核酸アナログ製剤を選択する症例が多い。
免疫抑制・化学療法中もしくは終了後のB型肝炎キャリアや既往感染者においては,免疫抑制の程度によりHBV DNAのモニタリングを1~3カ月ごとに行うが,HBV DNA量が20IU/mL(1.3LogIU/mL)以上となれば,すぐに核酸アナログ製剤(TAFもしくはETV)による治療を開始する。
未治療のHIV感染者に対してHBV感染に対する核酸アナログ製剤を単独投与すると,HIVが薬剤耐性を獲得する可能性があるため,HBVに対して核酸アナログ製剤を使用する前には再活性化予防の際も含め,HIV感染症合併の有無を確認する。

残り1,526文字あります
会員登録頂くことで利用範囲が広がります。 » 会員登録する