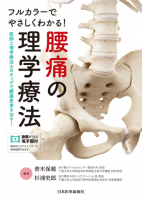お知らせ
【識者の眼】「厚底シューズと競技記録、故障」鳥居 俊
陸上競技においてランニングシューズやスパイクシューズは記録の向上と関連するだけに、誰もが最新の高機能のシューズを利用したいと考えるでしょう。陸上競技関係者ならずとも、マラソンや駅伝では出場選手の大部分が厚底シューズを着用することを知っていることと思います。厚底シューズの何が記録向上をもたらすか、というと、靴底の内部に爪先からカーボン製のプレートが挿入されており、この弾性によって推進力が増すということです。実際、世界の長距離界で記録は数%高まり、最近はトラック種目で使用できるシューズの底の厚さに制限が設けられるようになりました。さらには、高校生や中学生までもがこのようなシューズを着用して試合に臨むようになっています。
義足のパラリンピアンで男子走り幅跳び世界記録保持者のマルクス・レーム選手が以前、健常者のレースへの参加を申請したところ、義足がパフォーマンスを高めうる、として却下されたことがあり、「義足は厚底シューズと同じ」と読売新聞の取材に答えた、という記事があります(読売新聞オンライン5月26日)。それだけに、競技の公平性、公正性という点で競技力ほう助になる可能性のあるシューズの着用はルールで規制する必要が生じるわけです。

私は週1回、一般病院のスポーツ外来で陸上競技選手を多く診察していますが、20年前や10年前に比べて長距離走選手が受傷する故障の部位が変化している印象を持ち、実際に診療録から集計してみたところ、骨盤から股関節付近の故障が明らかに増加していました(2022年日本臨床スポーツ医学会で報告)。もちろん、厚底シューズの使用増加と時期を同じくしたから、故障の部位の変化の原因が厚底シューズにあると決めつけるのは非科学的ですので後ろ向き調査で検討したところ、厚底シューズを着用するようになって最も増加した故障部位が股関節部であることが判明しました1)。しかし、股関節部の故障が増加するメカニズムを直接に説明できていなかったため長距離走を専門とする選手たちにトレッドミル上で走ってもらいランニング動作の分析を行ったところ、同じ速度で走っても厚底シューズでは接地時間が短縮し股関節の動きが変化しているようだという結果になりました。短い接地時間で身体を推進することで作用反作用の結果身体に加わる負荷が高くなり、その負荷が股関節の動きを変化させたのだろうと考えました。
記録が向上する厚底シューズがもたらす問題は、股関節・骨盤部の故障が長引き、なかなか元のレベルに戻れない選手が少なくないことです。選手たちの身体に何が生じているのかを明らかにし、その原因を究明し予防策を打ち立てることが必要です。もしも選手の身体に不可逆的な変化を生じさせるようであれば、選手の健康を守る立場からシューズを規制することも必要です。ことに、身体発育途上の選手たちが記録の向上と引き換えに身体に治りきらない故障を受けるのであれば、選手生命を短くする危険が考えられます。現時点で厚底シューズが原因と断定はできませんので、慎重に研究や調査を重ねていくことにしています。
【文献】
1)植山剛裕, 他:日臨スポーツ医会誌. 2022;30(3):758-63.
鳥居 俊(早稲田大学スポーツ科学学術院教授)[ランニング障害][シューズ][股関節部]