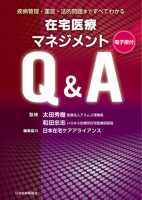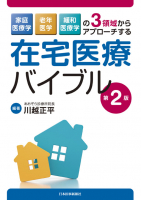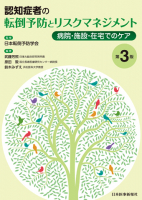お知らせ
予後予測(がん)[私の治療]
がん患者やその家族は死に至る経過について予備知識をほとんど持っていない。がん患者は最期の1カ月頃から様々な症状(食欲不振,呼吸苦,きつさ,嘔気など)が出現し,急速に悪化していく。このように経過が急なため,本人や家族に正確な予後を伝えることは,残された時間の有効な過ごし方の手助けになる。そのため,より正確な予後予測指標が望まれる。また,医師はがん患者や家族に予後予測を長く伝える傾向があり1),在宅開始時には予後の修正が必要なことがある。
▶予後予測
【予後予測指標】
がん患者の代表的な予後予測指標には,1)PaPスコア(palliative prognosis score),2)PPI(palliative prognostic index),3)PiPSモデル(prognosis in palliative care study predictor models)などがあり,予後を「日」「週」「月」の単位で予測する。
1)PaPスコア:主治医の主観的な予測やADL,食欲不振や白血球数などで予後を算出する。ただ,主治医の主観が得点の大きな部分を占め,経験が浅い医師には不向きで,採血も必要である。
2)PPI:以下の5つの予後指標に点数をつけ予後を予測する1)。① PPS(palliative performance scale):起居・活動と症状・ADL・経口摂取・意識レベル,②経口摂取量,③浮腫,④安静時呼吸苦,⑤せん妄の有無。
評価:合計得点6点以上で予後3週間未満の確率は感度83%,特異度85%と高い。この指標は採血が不要で,在宅でも簡便にできる。
3)PiPSモデル:採血検査結果が不要なPiPS-A,必要なPiPS-Bがある。データを入力すると14日生存率,56日生存率が表示され,採血を行っていればより精度の高い予後予測がわかるが,計算が複雑である。
【各指標の比較】
前述の3つの予後予測指標を終末期がん患者2462人に用いた大規模な報告1)では,3つの指標とも約70~80%の精度があり差は小さい。ただ,全体でPPIがやや低い傾向だが,短期生存(3週間以内)ではほかの指標と予後予測に差がなかった。
このことから,在宅の現場では,採血の必要がないPPIが最も使いやすい。より精度を高めたいときは採血が必要なPaP,PiPS-Bを使用するが,在宅の終末期に頻回に採血するのは酷である。

残り1,076文字あります
会員登録頂くことで利用範囲が広がります。 » 会員登録する