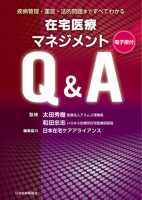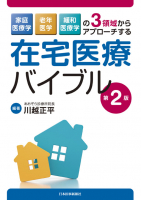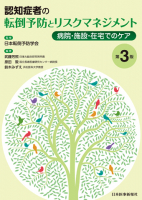お知らせ
維持血液透析の開始と継続に関する意思決定[私の治療]
日本透析医学会によると,2023年末の慢性透析患者数は34万3508人,過半数の患者が70歳以上であり,全体の9.2%の患者が入院中であることが報告されている1)。2019年に慢性透析患者の透析中止案件をめぐる訴訟があり,大々的な報道もあって,日本透析医学会は2014年公表の「維持血液透析の開始と継続に関する意思決定プロセスについての提言」を2020年に改訂した2)。この改訂において注目すべき点は,「事前指示(advance directive),共同意思決定(shared decision making:SDM),アドバンス・ケア・プランニング(ACP)」の概念や,さらに透析を導入しない,もしくは透析を中止することを意味する「保存的腎臓療法(conservative kidney management:CKM)および緩和ケアの提供」の概念を加えたことである。
▶医療者としての対応
【意思決定プロセスの変遷―事前指示からACPへ】
事前指示とは「意識がない状態に陥った際の医療行為についての希望を,意識が清明なうちに表明しておくこと」であり,わが国の透析現場では,いち早くその概念が普及した3)。その理由として,①週3回,1回4~5時間,長年にわたり同じ施設で透析を受けるため,スタッフとの会話の頻度が圧倒的に高い,②会話を通じて,スタッフが患者の生活観,死生観を理解していることが多い,③透析治療という生命維持治療を受けている一方で,同じ施設の他の患者の急変や死亡を体験していることから,医学的状況について一般人よりも理解が深い,④思いに変更が生じたとしても,週3回通院していることからスタッフに伝えやすい,などが影響していると考えられる。つまり「時間をかけた,繰り返しのACPが自然に展開されていた」ものと思われる。しかし,一般患者の間では,事前指示は普及せず,海外においても事前指示の有用性は評価されていない。

事前指示に代わる概念としてACPが登場し,わが国でも2018年に厚生労働省の肝いりで紹介されたが,事前指示を得ることのみにとらわれがちな医療・介護スタッフが多いことが指摘されている。そこで,Miyashitaらは「日本版ACPの定義と行動指針」を公表した。この中で「ACPは患者と家族等が話し合いを通じて,将来の心づもりをすることであり,医療・介護スタッフは,その話し合いの手助けをするのが役目である」ことが強調されている4)。

残り1,079文字あります
会員登録頂くことで利用範囲が広がります。 » 会員登録する