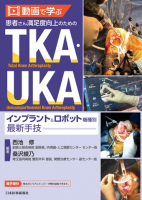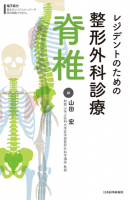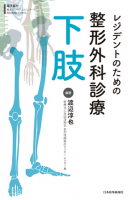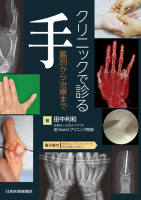お知らせ
凍結肩(五十肩)[私の治療]

凍結肩(frozen shoulder)は肩の痛みと進行性の可動域制限を生じる疾患で,一次性と二次性に分類される。一次性は明確な要因や外傷を伴わないもので,二次性は外傷,手術やその他の疾患(炎症性疾患など)を契機に発症するものである。3つの病期にわかれており,炎症期(inflammatory/freezing stage),拘縮期(frozen stage),回復期(thawing stage)の順に進行し,寛解する。多くの場合は自然軽快,または保存療法で軽快するが,高度な可動域制限が残存し難治性の症例では手術を要する。
▶診断のポイント
強い痛みと,それに伴う進行性の可動域制限,また関節包の炎症とそれに伴う線維化により全方向に制限をきたすことが特徴である。
腱板断裂,石灰性腱板炎,インピンジメント症候群などとの鑑別が必要である。まず問診で痛みの性状(夜間痛,安静時痛,動作時痛の有無)を聴取する。ついで可動域制限の有無とその傾向を評価する。インピンジメントをきたす腱板断裂や石灰性腱板炎では,下垂位外旋に比べ屈曲や外転の制限が強く出る傾向があるが,凍結肩では全方向性に高度な制限を生じる1)。疼痛の性状,可動域制限の程度と傾向を評価することで他の疾患との鑑別が可能となる。
前述したように凍結肩の病期は3期にわかれているため,どの期に受診したのかを判断する必要がある。炎症期の初期では,痛みの割に可動域制限が軽度の場合がある。したがって,初診時ではインピンジメント症候群の診断で経過観察中に高度な制限へと進行し,凍結肩と診断されることもしばしばある。また二次性では,糖尿病,心疾患,パーキンソン病,脳卒中などを合併していることが多く,原疾患のコントロールもしばしば必要となる。
画像診断では,単純X線で石灰の有無,肩峰や上腕骨大結節の骨棘を確認し,MRIや超音波検査で腱板断裂の有無を確認する。肩甲下筋腱の部分断裂は,MRIにおいてもしばしば見逃されるため,上腕二頭筋長頭腱症状が遷延する症例ではその存在を念頭に置いておく。

残り1,810文字あります
会員登録頂くことで利用範囲が広がります。 » 会員登録する