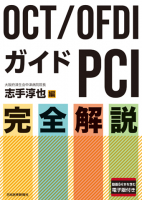お知らせ
川崎病(冠動脈病変)[私の治療]

川崎病は4歳以下の乳幼児に好発する血管炎症候群で,無治療では20~30%に冠動脈拡大・狭窄・冠動脈瘤などの冠動脈病変を合併する。早期に免疫グロブリン療法やアスピリン療法などの治療を行い,不応例にも迅速に対応すれば冠動脈病変の発生頻度は2~3%に抑制できる。冠動脈の内径4mm以下の局所性拡大所見を有するもの(5歳以上では周辺冠動脈内径の1.5倍未満のもの)を小動脈瘤,拡大,内径が4mm以上8mm未満のもの(5歳以上では周辺冠動脈内径の1.5~4倍のもの)を中等瘤,内径が8mm以上のもの(5歳以上では周辺冠動脈内径の4倍を超えるもの)を巨大瘤と呼ぶ。
▶診断のポイント
冠動脈病変の急性期の診断は主に心エコーで行う。冠動脈病変が検出された場合は,冠動脈の形態評価(冠動脈瘤の大きさ,狭窄の程度,冠動脈内血栓の有無など)と,それに伴う心筋虚血の評価などを行いながら,治療方針を決定する。

▶私の治療方針・処方の組み立て方
川崎病冠動脈炎は6~8病日頃に内膜および外膜の炎症細胞浸潤として始まり,10病日頃には動脈全層の炎症(汎動脈炎)に至り,動脈構築を保つ上で重要な構成成分である内弾性板や中膜平滑筋層が傷害され,12病日頃に動脈の拡張が始まるとされる。このため,10病日未満に炎症を収束させることが急性期治療の目標となるが,川崎病自体の急性期治療に関してはここでは割愛する。
心エコーでびまん性の冠動脈の拡大がみられ30病日までに正常径に戻る群(急性期の一過性拡大群)に関しては,遠隔期には原則として治療を必要としない。30病日を超えて残存する瘤が後遺症とされ(冠動脈瘤の残存群),虚血性心疾患の予防,血小板の活性化による血栓形成助長の予防目的で,抗血小板薬を継続して投与する。中等度以上の動脈瘤がある場合は,瘤における血栓予防の目的で抗凝固療法を追加する。中等度以上の瘤を形成した場合には発病1カ月以降に冠動脈造影を行い,以後,局所性狭窄の出現・進行に注意しながら定期的に評価を行うことが重要である。近年では低被ばく・高分解能の冠動脈CTの施行が可能になり,急性期・遠隔期を通じて詳細な冠動脈形態評価や瘤内血栓形成の有無の評価が可能になった。
小動脈瘤あるいは中等瘤は,発症から1~2年以内に縮小傾向を示し,冠動脈造影所見の正常化(退縮)を認めることが多い。ただし,退縮は増生した平滑筋細胞による見かけ上の正常化であり,将来的に冠動脈の狭窄や閉塞をきたす可能性があるため,注意して経過観察する。冠動脈の有意狭窄は主要冠動脈枝で内径75%以上の狭窄,左冠動脈主幹部で内径50%以上の狭窄とされており,有意な狭窄例では,心筋虚血症状が出現しなくても個々の症例の狭窄進行速度に応じて6カ月~数年の間隔で評価を行い冠動脈バイパス手術(coronary artery bypass grafting:CABG)や経皮的冠動脈インターベンション,ステント留置,ロタブレータなどの適応を検討する。その際には,形態的診断に加えて,運動負荷心電図・負荷心筋血流イメージング検査による心筋虚血の診断,血管内エコー法による血管性状の評価,ドプラワイヤー・プレッシャーワイヤーを用いた冠血行動態評価などを総合的に勘案し,適切な治療を選択する。負荷心筋シンチグラフィは心筋虚血の診断に関して,負荷心電図より感度が高く,非常に有用な検査である。運動負荷が行えない小児例ではアデノシンを用いた薬物負荷が行われることが多い。急性期の冠動脈瘤の内径が大きい症例では,2~5年ごとに負荷心筋シンチグラフィを行うことが望ましい。

残り1,014文字あります
会員登録頂くことで利用範囲が広がります。 » 会員登録する