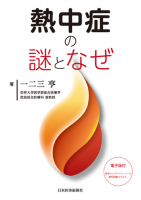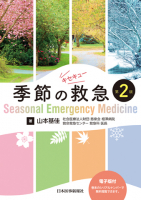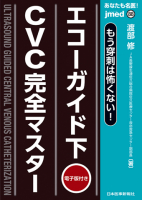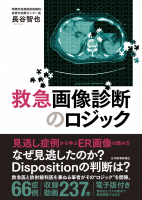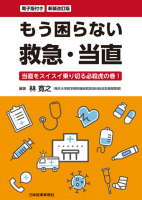お知らせ
呼吸困難[私の治療]
呼吸困難は主観的な表現であり,重症度も原因も様々である。A(気道),B(呼吸)の異常は短時間で心停止に至るリスクがあり,目の前の患者が致死的な呼吸困難かどうかの見きわめが最も重要である。緊急性の高い疾患を想起しながら原因検索・評価を行い,並行して速やかに安定化を図り,気管挿管のタイミングを見誤らないようにする。
▶病歴聴取のポイント
重症な呼吸困難であれば患者からの問診は困難である。バイタルサインのみならず,呼吸様式,皮膚所見,聴診所見など五感を駆使して診察する。また,家族など状況を知る人からの情報も欠かさない。
【問診】
まずは緊急性を判断するようなclosedな問診が求められる。発症様式,随伴症状,既往歴は診断の手がかりとなる。
【発症様式】
突然発症や急性発症には致死的疾患が多い。気道異物や肺塞栓症,緊張性気胸など「詰まった」「裂けた」「破れた」ような疾患を想起する。
【既往歴】
心疾患,呼吸器疾患の既往は特に重要であり,最近の治療状況や服薬コンプライアンスなども含めて問診する。また,薬剤性の間質性肺炎や肺胞出血などを疑うため,治療薬にも注意が必要である。精神疾患や過換気症候群の既往なども大切であるが,安易に心因性と判断しない。
【随伴症状】
発熱(気管支炎・肺炎など),咽頭痛・頸部痛(喉頭蓋炎・扁桃周囲膿瘍など),胸痛(急性冠症候群・肺塞栓・気胸・大動脈解離・心筋炎・胸膜炎・肋骨骨折),血痰,喀痰の増加,両上肢や口周囲のしびれ(過換気症候群),皮疹・下痢(アナフィラキシー)などの随伴症状は,原因の鑑別につながる。また,臥位での症状悪化や,夜間発作性呼吸困難などの体位や時間帯も重要な手がかりとなる。
▶バイタルサイン・身体診察のポイント
【バイタル】
SpO2は重要な指標であるが,容易に測定不良となる。呼吸数はとても重要であり,SpO2が維持されていても頻呼吸が持続する場合は注意が必要である。
【身体診察】
致死的な呼吸困難であるかの鑑別を優先する。特に呼吸補助筋の使用や網状皮斑,末梢冷感は緊急性のある疾患を疑う。気道狭窄音,呼吸音・心音,皮下気腫,頸静脈怒張など,緊急性の高い疾患を想起した身体所見から確認する。
視診:眼瞼結膜,口腔内・咽頭所見,皮膚(網状皮斑・蕁麻疹・チアノーゼ),呼吸様式(努力呼吸・呼気の延長・Hoover’s sign・起坐呼吸)
聴診:stridor/wheezes/crackles,聴診所見の左右差,心雑音
触診:気管偏位,皮下気腫,圧痛,末梢冷感,四肢浮腫
【SpO2モニターが測定不良なとき】
重症病態ではSpO2が測定不良で低値を示すことは多々ある。真の低酸素血症か判断するためには血液ガス分析は有用であるが,呼吸様式,末梢チアノーゼ・網状皮斑の有無から速やかに判断することもできる。

残り2,056文字あります
会員登録頂くことで利用範囲が広がります。 » 会員登録する