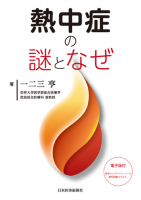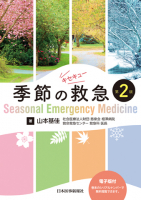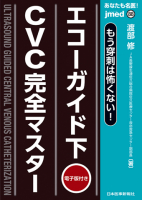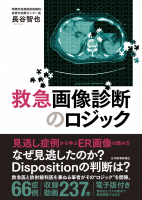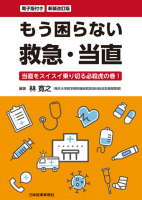お知らせ
吐血・下血・血便[私の治療]
消化管出血は日常診療で遭遇する緊急性の高い病態であり,迅速な初期対応と適切な診断・治療が求められる。消化管出血の治療では,患者の全身状態の安定化を最優先とする。循環血液量減少性ショックや進行性の貧血が認められる場合,速やかに輸液・輸血療法を開始する。同時に,出血源の同定と止血処置を行う。上部消化管出血では内視鏡的止血術が第一選択となるが,下部消化管出血では保存的治療で経過観察することも多い。ただし,持続する出血に対しては内視鏡的止血術や血管造影下塞栓術を,それでも止血できなければ外科的治療を検討する。特に,Forrest分類ⅠaやⅠbの活動性出血に対しては,クリッピング法やアルゴンプラズマ凝固法などの内視鏡的止血術を積極的に行う。
▶病歴聴取のポイント
病歴聴取では,出血の性状,量,頻度を詳細に確認する。吐血か,下血か,血便かの区別,鮮血か暗赤色か,タール便の有無などが鑑別に有用な所見である。また,腹痛,嘔気,めまい,失神の有無も確認する。既往歴では消化性潰瘍,肝硬変,炎症性腸疾患などがないか,服薬歴では抗血栓薬,NSAIDs,ステロイドの使用を確認する。特に近年は直接経口抗凝固薬(DOAC)の使用にも注意を払う。飲酒歴,最近の体重変化,排便習慣の変化も重要な情報となる。

▶バイタルサイン・身体診察のポイント
バイタルサインでは血圧と脈拍を測定し,理学所見を重視した全身状態の評価を行う。意識レベルや皮膚の蒼白,冷汗の有無が重要な所見となる。腹部の診察では圧痛や腫瘤の有無を確認し,直腸診では出血の性状や痔核の有無を評価する。また,肝性脳症や黄疸の有無も確認し,門脈圧亢進症による出血の可能性を考慮する。

残り1,683文字あります
会員登録頂くことで利用範囲が広がります。 » 会員登録する