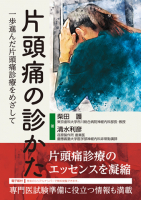お知らせ
■NEWS 【国際脳卒中学会(ISC)】ミノサイクリンが脳梗塞後の機能転帰を改善:大規模二重盲検RCT"EMPHASIS"

脳卒中後の後遺症軽減を目指し、神経細胞保護薬の開発は古くから進められてきた。しかしその有用性が、大規模ランダム化比較試験(RCT)で証明された薬剤は多くない。第2世代テトラサイクリンである「ミノサイクリン」もその1つである。
抗炎症作用を介した神経細胞保護が期待され、すでに有効性も報告されている。ただしいずれも動物実験や小規模非盲検RCTだった。しかし2月5日からロサンゼルス(米国)で開催された国際脳卒中学会(ISC)では、1500例以上を対象とした二重盲検試験"EMPHASIS"が報告され、同薬の脳梗塞後機能転帰改善が証明された。報告したのは、首都医科大学(中国)のYao Lu氏。

【対象】
EMPHASIS試験の対象は、発症後72時間以内の脳梗塞1724例である。「72時間以内」としたのは、その時点以降の神経細胞炎症亢進が報告されているからだという。
【方法】
これら1724例はミノサイクリン群とプラセボ群にランダム化され、二重盲検法で90日間観察された。ミノサイクリン、プラセボとも、ランダム化24時間後に200mgを静注し、その後は12時間おきに100mgを4日間与薬した。
【患者背景】
平均年齢は65歳、29%に脳梗塞既往があった。脳梗塞治療を見ると、経静脈的血栓溶解療法施行率は12%、血管内治療は2.4%のみだった。
【結果】
・有効性
その結果、1次評価項目である90日後の「mRS:0-1」患者の割合は、ミノサイクリン群(53%)でプラセボ群(47%)よりも有意に多かった。リスク比(RR)は1.11(95%CI:1.03-1.20)、治療必要数(NNT)は「17」である。「mRS:0-2」で比較しても同様で、ミノサイクリン群におけるRRは1.07(同:1.02-1.12)の有意高値、NNTは「22」だった。
・安全性
ランダム化後6日間の症候性頭蓋内出血に、両群間で差はなかった(ミノサイクリン群:0.3%、プラセボ群:0%)。また90日間の「血管系死亡」(1.2 vs. 1.9%)と「総死亡」(1.6 vs. 2.3%)も同様で、両群間に有意差はなかった。
【考察】
ミノサイクリンによる脳梗塞後機能転帰改善作用は、現在米中5つのランダム化比較試験で検討されている。現時点で最も早く終了が見込まれるのは、米国で進行している「NCT05032781」のようだ。
本試験は、中国国家自然科学基金委員会とBeijing Healthunion Cardio-Cerebrovascular Disease Prevention and Treatment Foundationから資金提供を受けた。