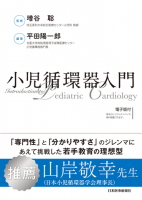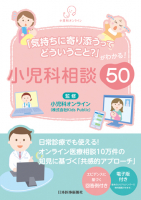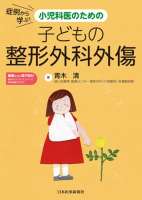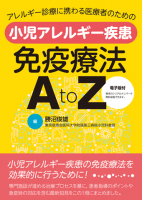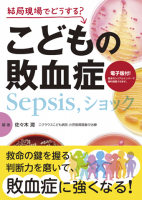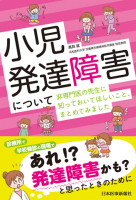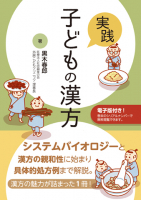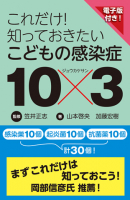お知らせ
【識者の眼】「総合診療と内科の違いは?」草場鉄周
No.5268 (2025年04月12日発行) P.61
草場鉄周 (日本プライマリ・ケア連合学会理事長、医療法人北海道家庭医療学センター理事長)
登録日: 2025-03-05
最終更新日: 2025-03-04
四半世紀にわたって、総合診療・家庭医療という分野の診療や教育に携わってきた中で、繰り返し耳にする問いかけが「総合診療と内科は一体何が違うのですか?」というフレーズである。特に、総合診療に関心を持つ医学生や若手医師がベテラン内科医からこう問われることで口ごもり、反論できずにアイデンティティを揺さぶられるという現象は津々浦々でみられる。その結果として、総合診療医・家庭医をめざすことを断念して、「最初は内科の臓器別専門領域をきわめて、どこかで開業して総合診療に進めばよいか」という古典的なキャリアへと誘導されることもめずらしくない。
私の立場からは、もちろんたくさんの相違点が見えるわけだが、ここ最近、その端的な実例を、私が運営する医療法人での実践から垣間見ることができたので紹介したい。それは小児に対する診療・ケアである。

いくつかの地域では小児科医が減少する中で不登校の児童に対して小児科や児童精神科の対応が難しく、家庭医のもとにたくさんの児童が受診するという状況が生まれている。心理面へのカウンセリングはもちろん、頭痛やめまいなどの身体症状へのケア、不安を抱える親へのサポートなど生物-心理-社会的アプローチが不可欠である。市町村の保健師や学校の保健教諭とのネットワークを構築して、チーム対応する機会も増えてきている。
また、こうした診療の延長線にある子育て支援や性教育、ライフスキルに関する地域活動は家庭医の得意分野である。学校医として学校に出向いて生徒に話をする教育講話、行政主導の地域プロジェクトのメンバーとして提供する保護者向けの講演やワークショップなど形式は様々だが、医療機関の壁を越えて地域に気軽に出向いていくという総合診療の地域アプローチは、医師・看護師を巻き込みづらい対象として見てきた現場の関係者の方からは大いに歓迎してもらえている。
最後に、小児への在宅ケアを取り上げたい。いわゆる医療的ケア児については小児科医の在宅診療がなかなか広まらないという現実に加えて、彼らが成人したあとのケアを誰が担うのかというトランジションの問題が深刻化している。医師が過剰な大都市部でさえ、この問題は解決できていない。そこで、年代を超えて幅広い疾患に対応し、在宅医療も得意とする総合診療医の役割がクローズアップされている。ある診療所では40名程度の医療的ケア児の在宅ケアに携わり、大学病院や総合病院の小児科、さらには行政とも連携しながら広域での小児在宅ケアのネットワークづくりに貢献している。
こうした事例を検証すると、内科との違いは鮮明であり、総合診療が得意とする世代を超えて連続性を持つ診療が、日本でも大きな役割を果たすことがわかってくる。大切なのは、こうしたケースを例外とせず、一般化して普及させ、医学生・若手医師を含む多くの方に知ってもらうことだろう。
草場鉄周(日本プライマリ・ケア連合学会理事長、医療法人北海道家庭医療学センター理事長)[総合診療/家庭医療]