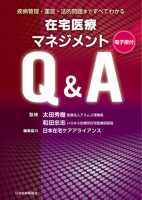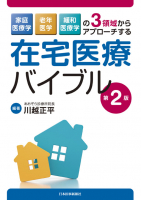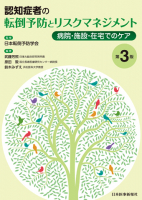お知らせ
医療的ケア児の人工呼吸器管理[私の治療]
医療技術や機器の進歩とともに,新生児集中治療室(NICU)・小児集中治療室(PICU)退院後に,人工呼吸療法を含むケアを継続しながら在宅療養や就学する小児が増えている。進行性の神経筋疾患も同様である。
▶治療の考え方
安定した在宅療養・就学を続けるために,呼吸状態や栄養状態の管理が重要である。

▶状態の把握・アセスメント
NICU・PICUでの急性期治療において,気管切開下人工換気(tracheostomy invasive ventilation:TIV)の導入後,状態がおおむね安定し,家族等が医療的ケア(人工呼吸器の取り扱い,痰吸引,栄養・薬剤投与など)の手技を習得できた状態で在宅療養に移行する。在宅療養でもSpO2をモニターしている場合がほとんどであり,SpO2低下時の初期対応は家族等でできる場合が多い。胸部聴診は,長期臥床に伴い背部に分泌物が貯留していることが多いため,前胸部だけでなく背部も行う。画像検査では胸部単純X線だけでなく胸部CTが有用な場合がある。
神経筋疾患(筋ジストロフィー,先天性ミオパチー,脊髄性筋萎縮症等)では乳児期からTIVが必要な重症例がある(脊髄性筋萎縮症1型に対しては,オナセムノゲンアベパルボベクやヌシネルセンによる乳児期や発症前治療が成功し,TIVが不要となった)。重症例以外でも筋力低下の進行とともに夜間の非侵襲的人工換気(non-invasive ventilation:NIV)が必要となる場合が多い。起床時の倦怠感や頭痛がある場合は,夜間の低換気の可能性があるため注意が必要である。日中の呼吸状態の評価(胸部聴診,SpO2)だけでなく,夜間の呼吸評価(SpO2,睡眠ポリグラフ)も実施する。SpO2が保たれていても高炭酸ガス血症を呈している場合があるので,適宜,血液ガス分析や経皮二酸化炭素モニターを行う。

残り1,414文字あります
会員登録頂くことで利用範囲が広がります。 » 会員登録する