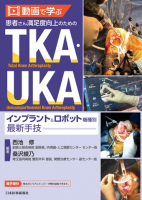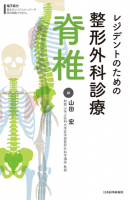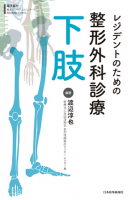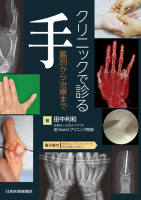お知らせ
扁平足(成人期)[私の治療]

様々な病因が組み合わさり,中高年になると有痛性扁平足をきたすことがある。成人期扁平足は近年,欧米ではPCFD(progressive collapsing foot deformity)1)と呼ばれており,A:後足部外反,B:中足部/前足部外転,C:前足部内反変形/内側列不安定性,D:距骨周囲亜脱臼/脱臼,E:足関節不安定性の各要素が影響し合いながら変形をきたしている。日本語では「進行性扁平足」と呼ばれる。
▶診断のポイント
上記のA~Eの要素の有無と,それぞれが可橈性であるか,硬くなり不橈性になっているかを評価する。典型的な例では,後脛骨筋腱が変性して不全断裂を起こすことが多いため,足関節の内果下方で後脛骨筋腱に沿って腫脹と疼痛を訴える場合は本症を疑う。進行すればPCFDのそれぞれの要素が組み合わさった変形をきたし,足内側の疼痛だけでなく,踵骨と距骨外側突起や腓骨の間でインピンジメントを生じて外側にも疼痛をきたすようになる。変形が長期に及ぶ場合には,関節拘縮を生じるため関節の硬さを評価することも重要である。後脛骨筋腱の断裂があれば片側つま先立ちが難しくなる。

画像診断としては,足縦アーチが低下すると荷重時足側面X線像にて距骨軸と第1中足骨軸のなす角(Meary角)が増大し,踵骨の下端線と足底面のなす角(calcaneal pitch角)が減少する。また前足部が外転すると,荷重時足正面X線像で舟状骨と距骨の関節面のなす距舟関節被覆角が大きくなる。超音波検査やMRIは,後脛骨筋腱やばね靱帯,三角靱帯の変性や断裂の診断に有用である。なお,正確に変形を評価するためには荷重CTが役立つ。
▶私の治療方針・処方の組み立て方
病状の進行の程度にかかわらず,まずは保存治療として運動療法ならびに足底挿板の処方を行う。保存治療が無効の場合には,手術治療を考慮する。足縦アーチが低下している場合はPCFDのA~Eの変形の程度と可橈性の有無を評価し手術方法を決定する。軟部組織修復や骨切り術など様々な術式があるが,目標としては後足部の冠状面アライメントに関して,踵接地時に踵骨軸と下腿軸が平行になるように踵外反を矯正する。また,下腿軸と垂直な軸が踵離床時に第2中足骨軸と平行になるように前足部外転を矯正する。

残り998文字あります
会員登録頂くことで利用範囲が広がります。 » 会員登録する