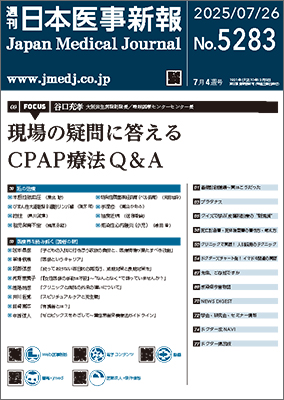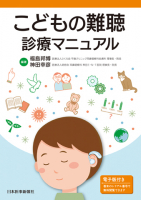お知らせ
機能性発声障害[私の治療]
嗄声(声がれ)や失声(ささやき声しか出せない状態)が生じているにもかかわらず,声帯粘膜の器質的異常に乏しく,声帯運動の麻痺が認められず,主に発声時の声帯の内転運動の過剰,あるいは不足のために声帯振動が乱されている状態を機能性発声障害と言う。声帯病変や声帯麻痺を「楽器自体の故障」とたとえるなら,機能性発声障害は「楽器の弾き方の異常」とたとえることができる。
▶診断のポイント
機能性発声障害は,過緊張性発声障害,低緊張性発声障害,ピッチ(音声の高さ)障害に大別できる。最初に患者に持続母音を発声してもらい,音声所見を聴覚心理学的に評価する(GRBAS尺度)。その後,内視鏡で喉頭を観察しながら,患者に母音発声と吸気を反復してもらい,声帯粘膜の異常,および声帯麻痺がないことを確認したあとに,発声時の喉頭の構えの異常,すなわち声帯過内転,声門上部圧迫,声帯内転不足に伴う声門閉鎖不全に注目する。粗糙性嗄声(ガラガラ声)/努力性嗄声,および発声時の声帯過内転/声門上部圧迫が認められれば過緊張性発声障害である。

一方,低緊張性発声障害では,失声/気息性嗄声(息が抜けたような声)/無力性嗄声に加えて,発声時の声帯内転の不足に伴う声門閉鎖不全が認められる。有声音が弱いながらも生じていれば音声衰弱症,ささやき声のみ出せる状態(失声)の場合には心因性失声症と診断される。なお,音声衰弱症では,喉頭所見に異常が認められず,呼気衰弱のみに起因することがあるため,喉頭所見が診断の手がかりとなりにくい。

残り1,732文字あります
会員登録頂くことで利用範囲が広がります。 » 会員登録する