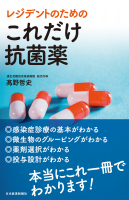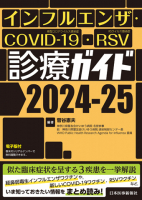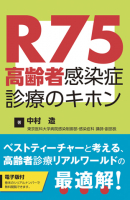お知らせ
狂犬病[私の治療]

狂犬病は,人獣共通感染症のひとつで,狂犬病ウイルスを保有するイヌなどの哺乳類に咬まれたり,引っかかれたりすることによって感染する。ほとんどがイヌによるものであるが,ほかにコウモリ,ネコ,キツネ,アライグマなどの場合がある。発症するとほぼ100%致死的であり,迅速な曝露後予防(post-exposure prophylaxis:PEP)が重要である。日本は世界的に数少ない狂犬病清浄国であるが,世界ではアジア,アフリカを中心に年間5万人以上が狂犬病で死亡している1)2)。
▶診断のポイント
狂犬病を有する動物に咬まれたり,引っかかれたりした病歴があれば,鑑別疾患に挙がる。臨床症状からの診断は難しく,渡航歴や活動歴などを参考にする。

【症状】
潜伏期は通常1~3カ月であるが,長い場合には1年以上になる。初期症状としては発熱,創傷部位のチクチク感,刺すような痛み,灼熱感などがある。中枢神経の症状が出た場合,狂躁型(furious rabies)と麻痺型(paralytic rabies)の2つの型がある。
狂躁型は多動,興奮,幻覚,恐水症状,恐風症状などを引き起こし,数日で死亡する。麻痺型は全体の約20%を占め,創傷部位から徐々に麻痺し,昏睡状態はゆっくりと進むが,最終的には死亡する。
【診断】
唾液,脳脊髄液を用いたPCR法によるウイルスゲノムRNAの検出によって診断する。感染を疑った場合には,保健所や国立感染症研究所に相談する。

残り2,027文字あります
会員登録頂くことで利用範囲が広がります。 » 会員登録する