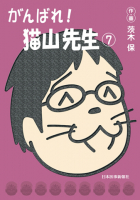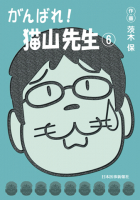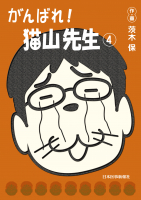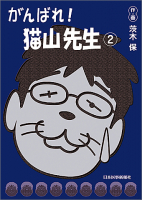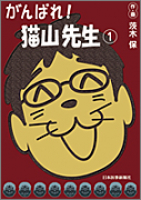お知らせ
幼児が間違いやすい 日本語の傾向とは?
【Q】
幼児が日本語を習得していく際の言い間違い,文法間違いの傾向などは既に研究で明らかになっているのでしょうか(私の子どもで一例を出せば,「ひきずらない」と言うべきところを「ヒキズルナイ」などがあります)。 (兵庫県 K)【A】
結論から言えば,幼児の発話に生じる誤りの「傾向」は先行研究でかなり明らかにされています。ただ,それらが「本当に示唆しているもの」についてはまだ議論が続いている,となりましょうか。幼児の言い間違い・文法間違いは多くの場合,成人のものとは性格が異なります。それらは「うっかり」間違いではなく,その時点までに彼らのことばに関する知識が到達した場所を示す指標,「暫定的な正しい形」です。ですから,彼らに成人の文法からみた正用を指摘しても素直に訂正に応じてはくれません。また,周囲の大人はしていない形が出てきますから単純な模倣ではないことにも注意して下さい。
例をいくつかみていきましょう。まず,ご報告下さった「ヒキズルナイ」はいわゆる終止形に否定辞が直接くっついてしまった誤りです。いかにも子どもがやりそうな,ということで「タベルナイ」なども言うのだろうと予想すると大外れ。後者の誤りはほとんど観察されないことが知られています。これには,子音終わりの語根(hikizur-)と母音終わりの語根(tabe-)の対照が大きく関わっています。そして3歳前の子どもでもその区別は知っていることがわかります(文献1)。
次は,3歳児の発話から例を挙げます。「(ゲームの的をさして)コレニアタッテ」は成人の文法なら「これに当てて」です。こうした自動詞─他動詞交替もよく観察される誤りです。ここにも自動詞を他動詞の代わりに使うほうが時期も早く,頻度も高いという非対称性がみられることが知られていて,素性と動詞句構造の観点から理論的研究が進められています(文献2)。
もう1つ有名なのが「アカイノクツ」に代表される「ノ」の過剰使用の誤りです。これは「たけちゃんのくつ」のような格助詞の連体修飾が過度に一般化されたものなのか(文献3),あるいは補文標識なのか(文献2),はたまた準体助詞の名詞的用法からの類推なのか(文献4),「ノ」の正体を巡って議論が続いています。
音韻的な間違いの傾向にも目を向けておきましょう。「オタカヅケ」(お片づけ)や「エベレーター」(エレベーター)のような誤りでは,比較的長い語の真ん中あたりで,隣接する,共通の母音を持つ音節間で,音声的によく似た子音同士の転換が起こりやすいことがわかっています(文献5,6)。この例では音の組み立て作業の規則性が垣間見えます。これらの誤りは,言語習得過程にある子どもの心・頭の中で進行中の何かを教えてくれる重要な資料の1つと言えます。
【文献】
1) Sano T:Roots in Language Acquisition:A Com-parative Study of Japanese. Hituzi Syobo, 2002, p75-81.
2) 村杉恵子:ことばとこころ─入門 心理言語学. みみずく舎, 2014, p36-48.
3) Clancy P:The Acquisition of Japanese:The Crosslinguistic Study of Language Acquisition. Volume 1. Psychology Press, 1986, p373-524.
4) 柴谷方良:理論研究と習得研究をつなぐもの─準体助詞「の」と誤用「赤いのくつ」をめぐって. 慶應言語学コロキアム講演資料, 2010.
5) 寺尾 康:言い間違いはどうして起こる?. 岩波書店, 2002.
6) 伊藤克敏:こどものことば─習得と創造.勁草書房, 1990.