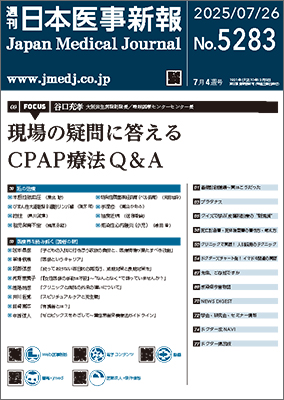お知らせ
低用量ピルと血栓塞栓症
【Q】
低用量ピルの副作用としての血栓塞栓症について,産婦人科開業医として注意すべき点,初回処方(定期検診時)のチェックポイント,対策などを,飯田橋レディースクリニック・岡野浩哉先生に。【質問】
江夏亜希子:四季レディースクリニック院長
【A】

投与前の問診はきわめて重要です。既知の血栓性素因を有する場合や,血栓性静脈炎,深部下肢静脈血栓症(deep vein thrombosis:DVT)および肺塞栓(pulmonary embolism:PE),脳血管障害,心筋梗塞の既往歴を有する場合は投与禁忌です。
血栓症の家族歴を有している場合は慎重投与となりますが,リスクは約2倍増え,家族が50歳未満に発症している場合や複数の家族に血栓症既往が認められる場合はさらに上昇します。高血圧症,糖尿病(耐糖能異常),肥満,喫煙などの既往歴もリスク上昇に寄与します。稀ではありますが,悪性腫瘍の罹患,麻痺や手術などによる不動は強い誘発因子ですので使用中止が必要となります。動脈血栓である血栓性脳卒中(脳梗塞)のリスク因子として片頭痛があります。片頭痛の好発年齢はOC/LEPを使用する年齢層と重なるため注意が必要です。特に前兆を伴う片頭痛では投与禁忌となっています。
上記内容を必ず問診で確認し,カルテ記載とリスク評価を行い,適合者に投与することが安全性確保の第一歩です。
投与中の管理として,投与前に存在しなかった上記リスク因子が投与中に新たに出現してくることがあります。40歳以上は慎重投与に分類されますが,知らぬ間に慎重投与例に処方していることになりかねません。そのため,問診によるリスク評価は最低でも年に1度は行うべきです。血栓症の中でもDVTは多く認められ,PEの基礎病態です。そのため,片側性の下肢の腫れや痛み,発赤,つれ,重だるさなどの訴えがあった場合は,下肢の所見を必ず取るべきです。
ポイントは片側性ということで,患側だけの,下肢静脈に沿った限局性の圧痛,下腿周囲径増大(健側に比し3cm以上),陥凹を示す浮腫,表在静脈の側副路形成の有無をチェックします。これらが明らかな場合は直ちに下肢静脈エコー検査による血栓の有無の確認が必要です。欧米の管理基準では,所見がない場合はDダイマーを測定し,陰性の場合DVTは否定的であり,陽性の場合は下肢静脈エコー検査を行うこととなっています。
予知検査がないということは,早期発見・早期治療が重篤な転帰を回避する最大の防御となります。そのための第一段階は患者教育です。血栓症を疑う初期症状の頭文字をとった“ACHES”(腹痛,胸痛,頭痛,眼症状,下肢痛:abdominal pain,chest pain,headache,eye disorders,severe leg pain)の周知とその際の連絡を徹底させることが重要です。緊急性がある場合は,循環器科または脳神経外科への受診を促し,血栓症リスク症例であることの情報提供を行うか,患者自らが申告できるように指導すべきです。これら血栓症の診断・治療を行ってくれる施設との,連携体制の構築は患者を守る最大の対策となります。