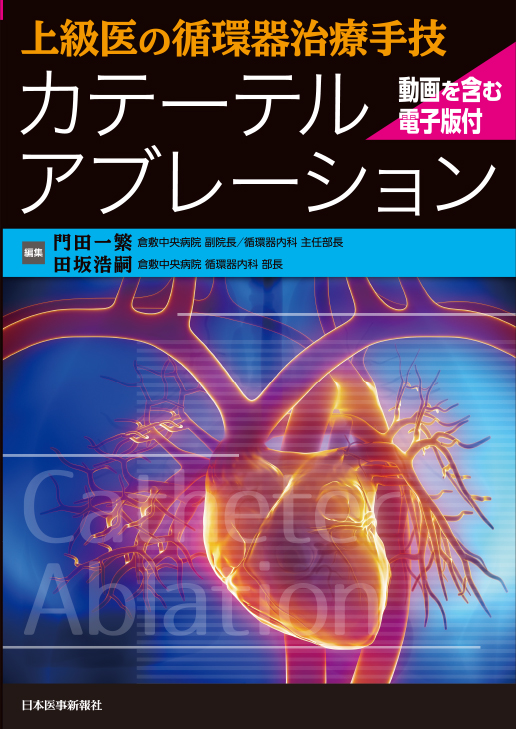jmedmook
お知らせ
上級医の循環器治療手技 カテーテルアブレーション【動画を含む電子版付】
39本の動画でわかりやすく解説
| 編集: | 門田一繁(倉敷中央病院 副院長/循環器内科 主任部長) |
|---|---|
| 編集: | 田坂浩嗣(倉敷中央病院 循環器内科 部長) |
| 判型: | B5判 |
| 頁数: | 212頁 |
| 装丁: | カラー |
| 発行日: | 2019年08月23日 |
| ISBN: | 978-4-7849-6270-9 |
| 版数: | 第1版 |
| 付録: | 無料の電子版が付属(巻末のシリアルコードを登録すると、本書の全ページを閲覧できます) |
目次
1章 クライオバルーンアブレーション
1 肺静脈隔離は単回3分間冷却で十分か?─どのような症例に追加冷却をすべきか?
2 下肺静脈にて近位部までachieve guide wireを引いてもPV電位が確認できないときの冷却テクニックは?─PV電位指標or最低温度指標
3 良好な肺静脈閉塞造影を確認できても冷却中の温度低下が十分でないときもしくはPV電位が消失しないときの対処法
4 クライオバルーンによる肺静脈隔離後にATPによるdormant conductionが出現した場合,再度クライオバルーンアブレーションを行うかor高周波タッチアップを行うか?
5 腎機能不良例またはアレルギー例において造影剤を使用せずにクライオバルーンアブレーションを行った症例
6 PV anomalyを認める症例に対するバルーンテクニック(左共通幹,右中肺静脈症例)
7 左下肺静脈冷却時に最低食道温度が何℃を下回った場合,冷却を中止すべきか―食道合併症の予防
8 EnSite NavXTMを用いたCMAPモニタリングの有用性─呼吸変動と右横隔神経麻痺の見きわめ
9 空気塞栓による心電図ST上昇や血圧低下が起きた場合にどうするか?─その対応と予防法について
10 左上肺静脈冷却後の迷走神経反射による高度徐脈に注意する
2章 高周波アブレーション
1 持続性心房細動においてlow voltage zoneの焼灼が有効であるのはどのような症例か
2 下非発作性心房細動においてrotorアブレーションが有効と思われるのはどのような症例か
3 心内膜側からの通電にて僧帽弁峡部のブロック作成に難渋する場合の対処法は?
4 コンタクトフォースガイド下拡大肺静脈隔離において,ライン上で隔離を達成するのが困難な場合の対処法は?
5 肺静脈隔離後のATPによるdormant conduction確認を行う至適なタイミングは?
6 肺静脈隔離後にイソプロテレノール負荷にて出現するnon-PV fociをどこまで追いかけるか?
7 3DCT imageを参照にした左肺静脈-左心耳間anterior-ridge焼灼のコツ
8 肺静脈再伝導を認めない再発性心房細動に対する治療戦略
9 心房細動アブレーション治療としてのMarshall静脈への化学的アブレーションの位置づけは?
10 流出路起源心室性期外収縮に対する多面的アプローチ
3章 ホットバルーン
1 高周波ホットバルーンを用いて拡大肺静脈隔離を行うには
2 高周波ホットバルーンアブレーションにて慢性期肺静脈狭窄を避けるための工夫は?
4章 その他
1 アブレーション中の鎮静は意識下鎮静,または深鎮静いずれを選択すべきか? 鎮痛薬は併用すべきか?
2 アブレーション周術期における至適な抗凝固療法は?
3 アブレーション施行後フォロー中に無症候性心房細動を見つけた場合にどうするか?
4 非通常型心房粗動や術後心房頻拍における多極マッピングのコツと手技のエンドポイントは?─multiple ATや広範なscar症例の場合
序文
循環器診療における低侵襲の治療として,PCI,カテーテルアブレーション, さらにはTAVIやMitraClipなど, 様々なカテーテル治療が発展し,主流を占めるようになってきている。カテーテル治療では特に術者の教育やトレーニングが重要であり,各施設でこれまでの経験を活かした取り組みが行われている。現在,デバイスの進歩は目覚ましく,また,新たな手技の工夫もされ,より高いレベルをめざすには施設の枠を超えた形での教育,トレーニングの方法が必要となっている。そのために,ライブデモンストレーションやビデオライブなどに参加することも考えられるが,限界もある。
さて今回,多くの方のご協力で,『上級医の循環器治療手技 カテーテルアブレーション』 を上梓させて頂いた。エキスパートの先生方に,実臨床で遭遇する様々な症例における手技の実際とポイントを解説頂き,また多くの症例に動画をつけることで,ビデオライブのような側面も持たせた。それぞれの手技には各先生のこれまでの経験に基づいた理論があり,それをもとにした治療の工夫を学ぶことのできる教育ツールになっている。
本書の循環器治療手技はカテーテルアブレーションであり, 編集に当たっては当院の田坂浩嗣医師に協力をお願いした。編者として原稿を読ませていただく中で,各先生のカテーテルアブレーションに対する深い思いと論理性を随所に感じ取らせて頂いた。本書を活用し,ぜひ理論と実践を深め,カテーテルアブレーションの上級医をめざして頂ければ幸甚である。
2019年7月
倉敷中央病院 副院長/循環器内科 主任部長 門田一繁