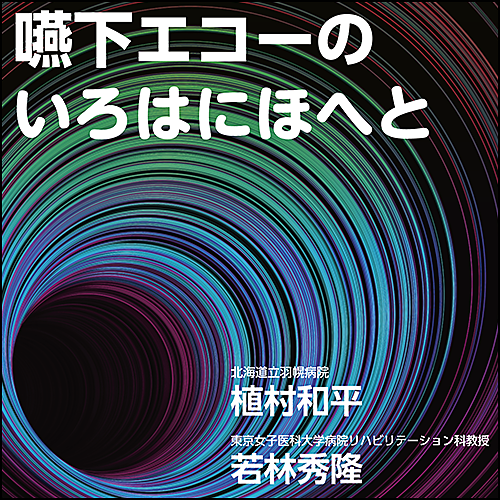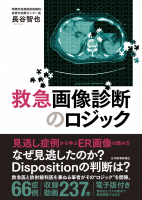お知らせ
特集:便秘エコーのいろはにほへと


2017年自治医科大学卒業。北海道家庭医療学センターの総合診療専門医プログラムに所属。現在栄町ファミリークリニック。エコー大好きレジデントで,“エコレジ”と称して活動中。

1 便秘における画像検査のあれこれ
便秘に対してどの検査を使うか,もしくは検査をせずに判断する状況も多々あると思いますが,以下のものが検査をする場合に考慮されると思います。
・XP:熟練の目が必要で,X線が取れる環境が必要
・CT:視認性に優れるが,コストや放射線被ばくを考慮すると, 気軽には撮影できない
・世界消化器病学会推奨の専門検査:日本では保険適用されていないものがほとんどで,検査器具も導入されているところは少ない
・エコー:ポイントを押さえればお手軽でどこでも誰でもできる
2 便秘エコーでどこまで見える?
・意外と知らない腸管生理
・エコーで結腸の生理学的運動にせまる
便秘の時は水を飲むのが一見良さそうですが,小腸と大腸の水分吸収量について考えてみると意外とそうでもないのかもしれません。腸管生理を振り返ってみます。そして一口に腸管運動といっても蠕動,分節,振り子の3種類に分けられます。小腸は常に蠕動しており,聴診でもその蠕動音を聴取することは容易ですが,大腸は蠕動が乏しいことが知られています。しかし食後には結腸の蠕動が亢進するので,通常は観察しにくい結腸の蠕動もエコーで観察できます。また,恥骨直腸筋により直腸の角度が変化する様子もエコーであれば観察することができます。
3 診断と治療戦略
・臨床医の姿勢:器質的疾患の除外
便秘の診療にあたって機能性便秘の診断の際には, 器質的疾患を除外しようとする姿勢が当然ではありますが大事です。高齢者の最近発症の便秘には特に注意で,red flag signを念頭に置きながら診療にあたる必要があります。
・エコー戦略:直腸にあるのかないのか。さらに追究できるか?
エコーを用いた便秘診療は, 病態評価や治療効果判定も可能で非常に優れものです。しかし最初の慣れないうちはどこから始めたらよいかわからなくなってしまうのも事実です。そこで筆者の私見ではありますが,エコーの走査手順,診断と治療戦略をご紹介します。
4 具体的な症例集
・異常症例で目を慣らす
・エコーで見てみる:大人も子どもも。外来から病院, 在宅も
まず正常症例でエコー解剖に慣れる必要がありますが,次に必要となるのが異常症例を見る目を肥やすことです。エコーの画像や動画を載せていますので,一緒に見ながら繰り返し解剖と異常像に慣れてゆきましょう!
5 結論:まずは恥骨下アプローチから始めよう!
レベル1 恥骨下アプローチ:あるのかないのか,刺激が必要なのか?
直腸内部に便があるかないかの存在診断です。次に便意を感じるかどうか。なければ直腸刺激が必要なのでは,と考えます。
レベル2 便性状評価:硬いのか軟らかいのか,便性状への介入は?
エコーでの質的評価となります。エコーの画像上直腸や結腸内部が高エコー像で音響陰影を伴うようであれば,硬便であり,排便困難感を自覚していればなおさら便性状に対する治療介入が必要と考えます。
レベル3 結腸アプローチ:腸管の評価,器質的疾患はあるのだろうか?
さらに慣れてくれば,直腸から結腸をスクリーニング走査し,腸管の壁構造や周辺情報を加味し,病態判断を行います。便秘の原因となる器質的疾患をエコーでスクリーニングすることが本稿の最終目標になります。